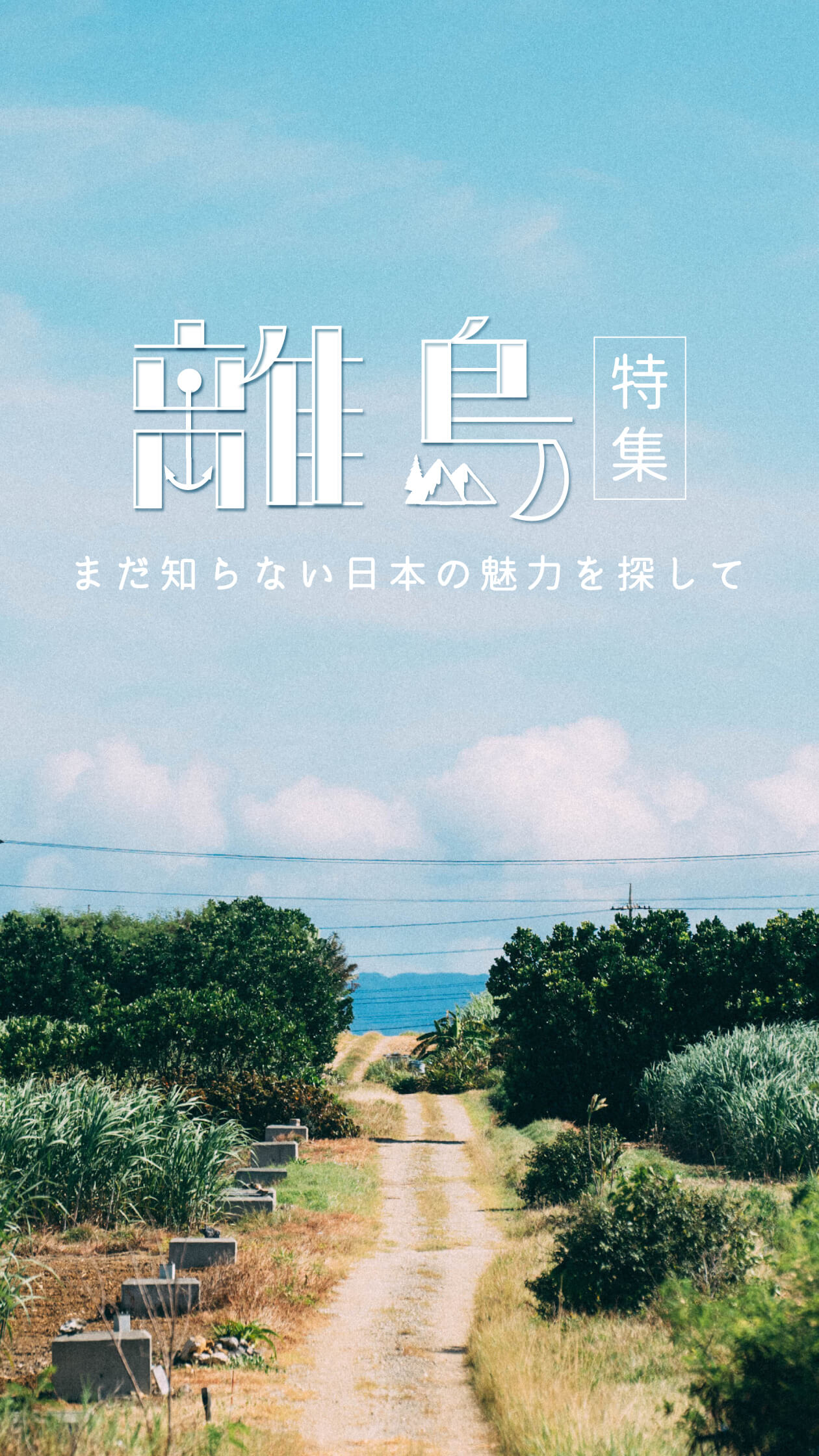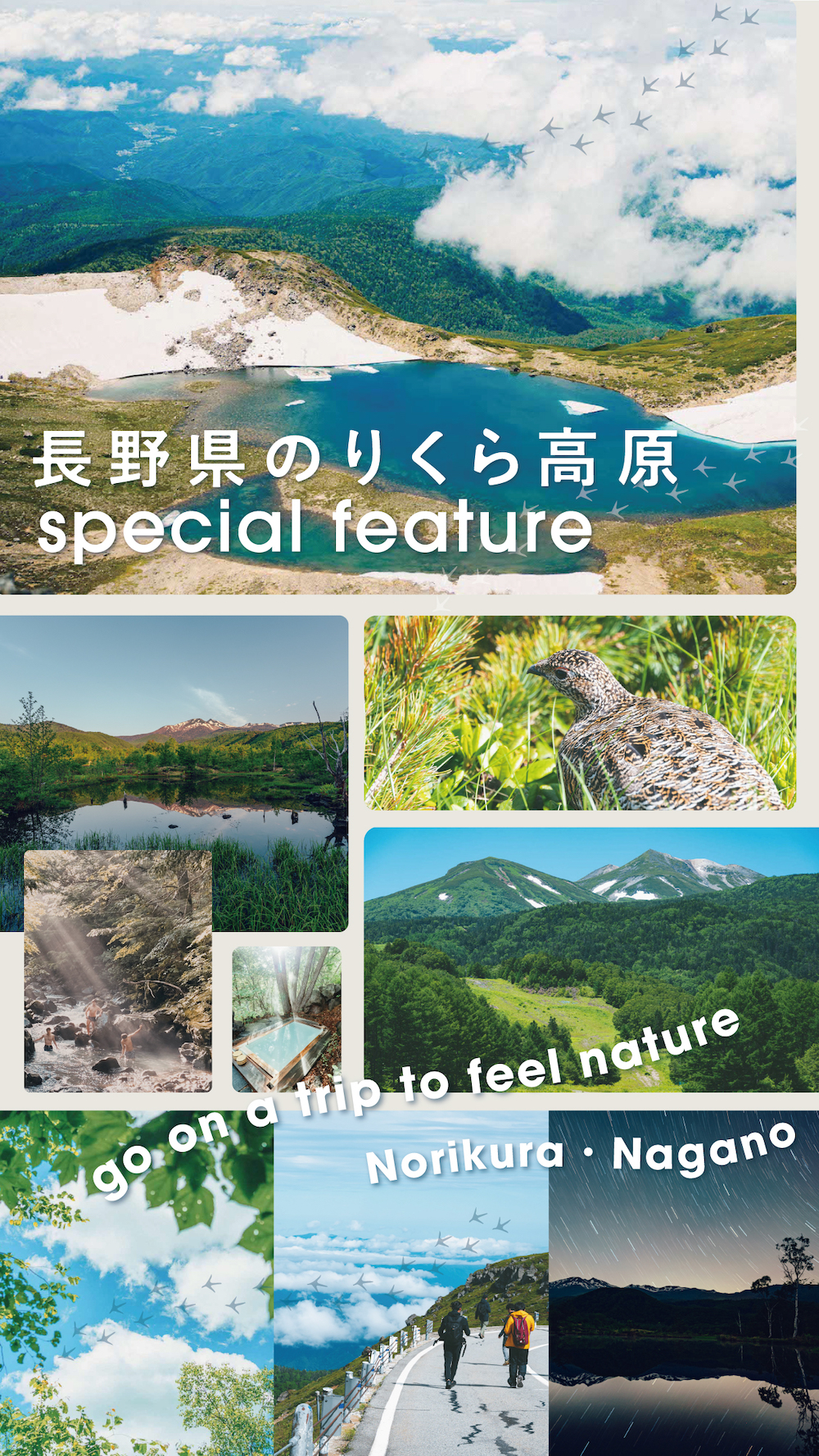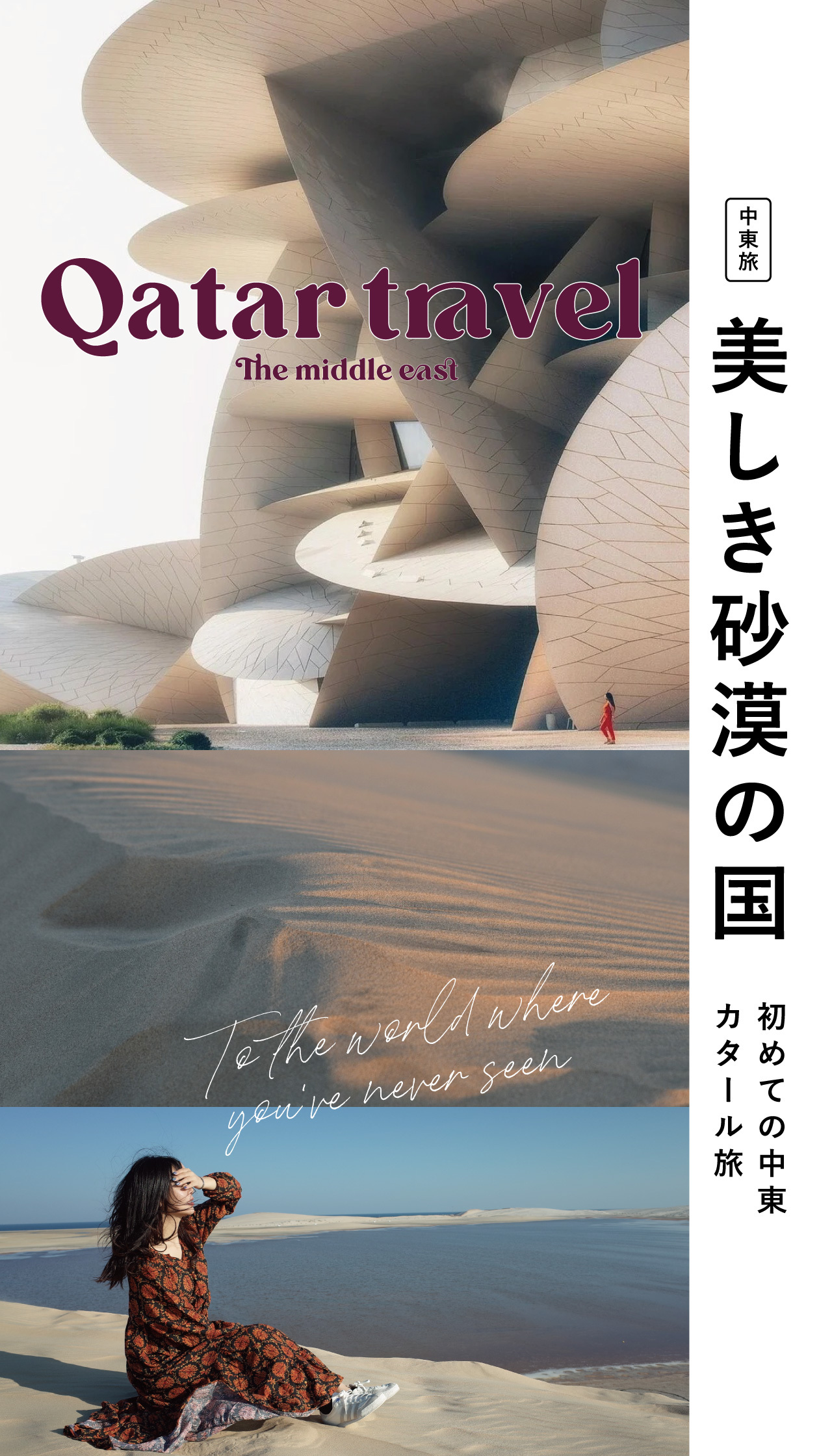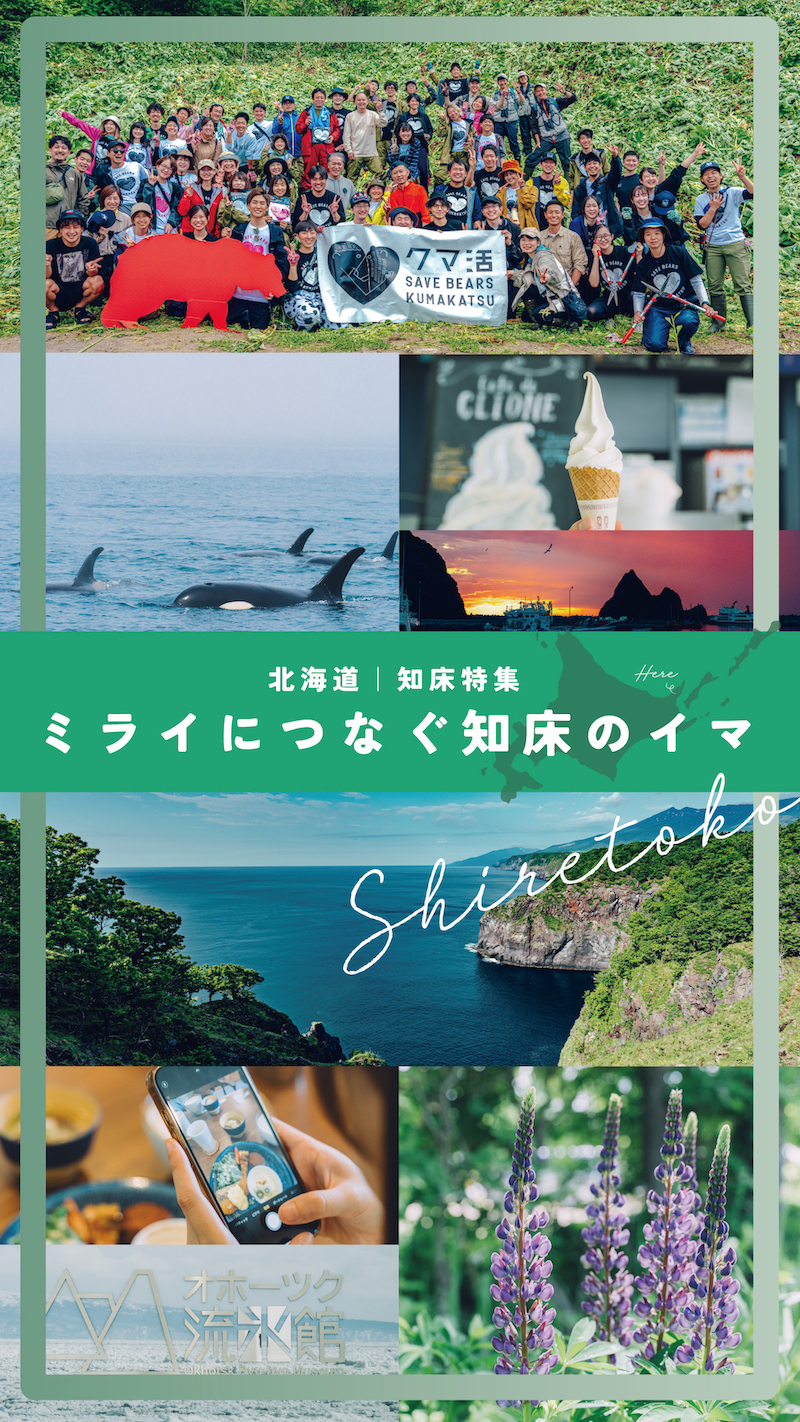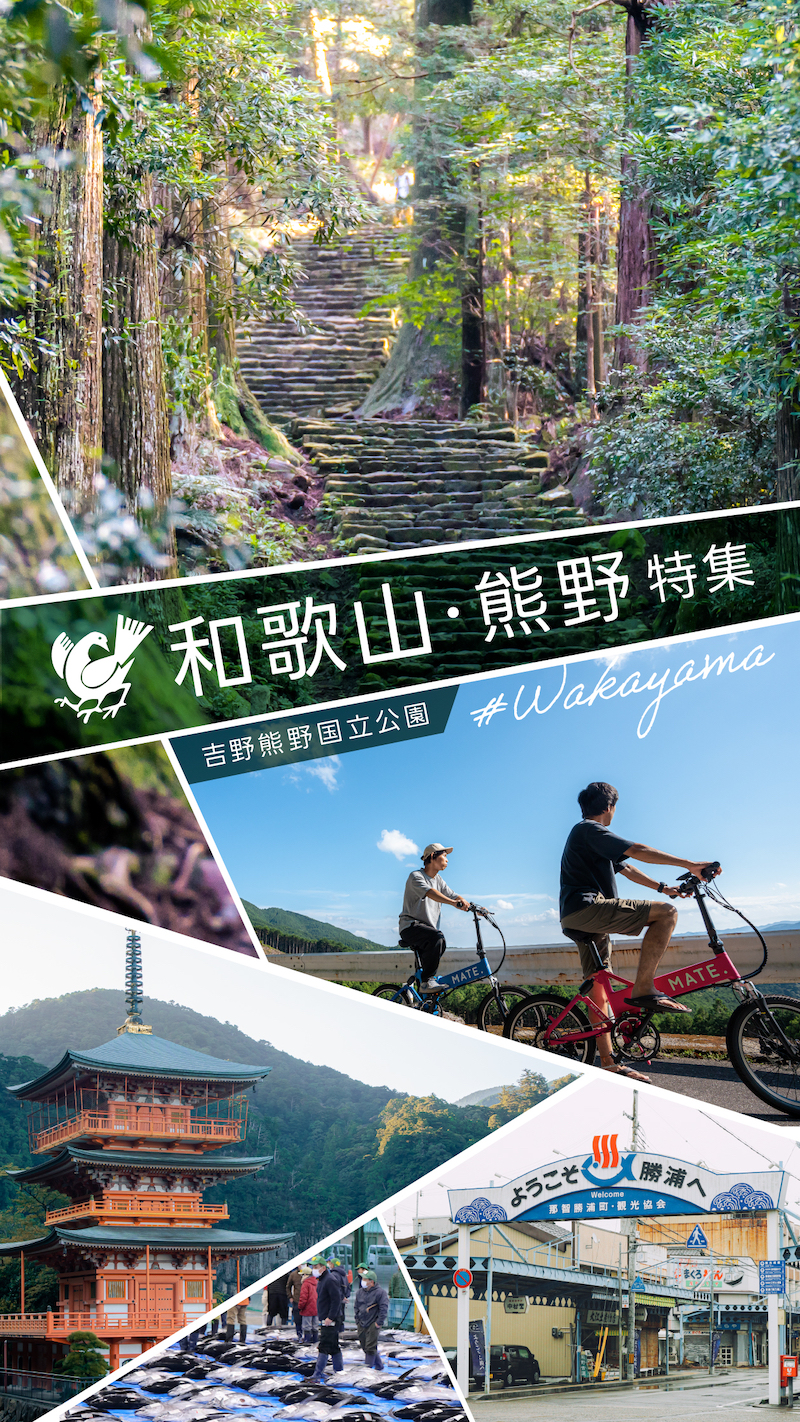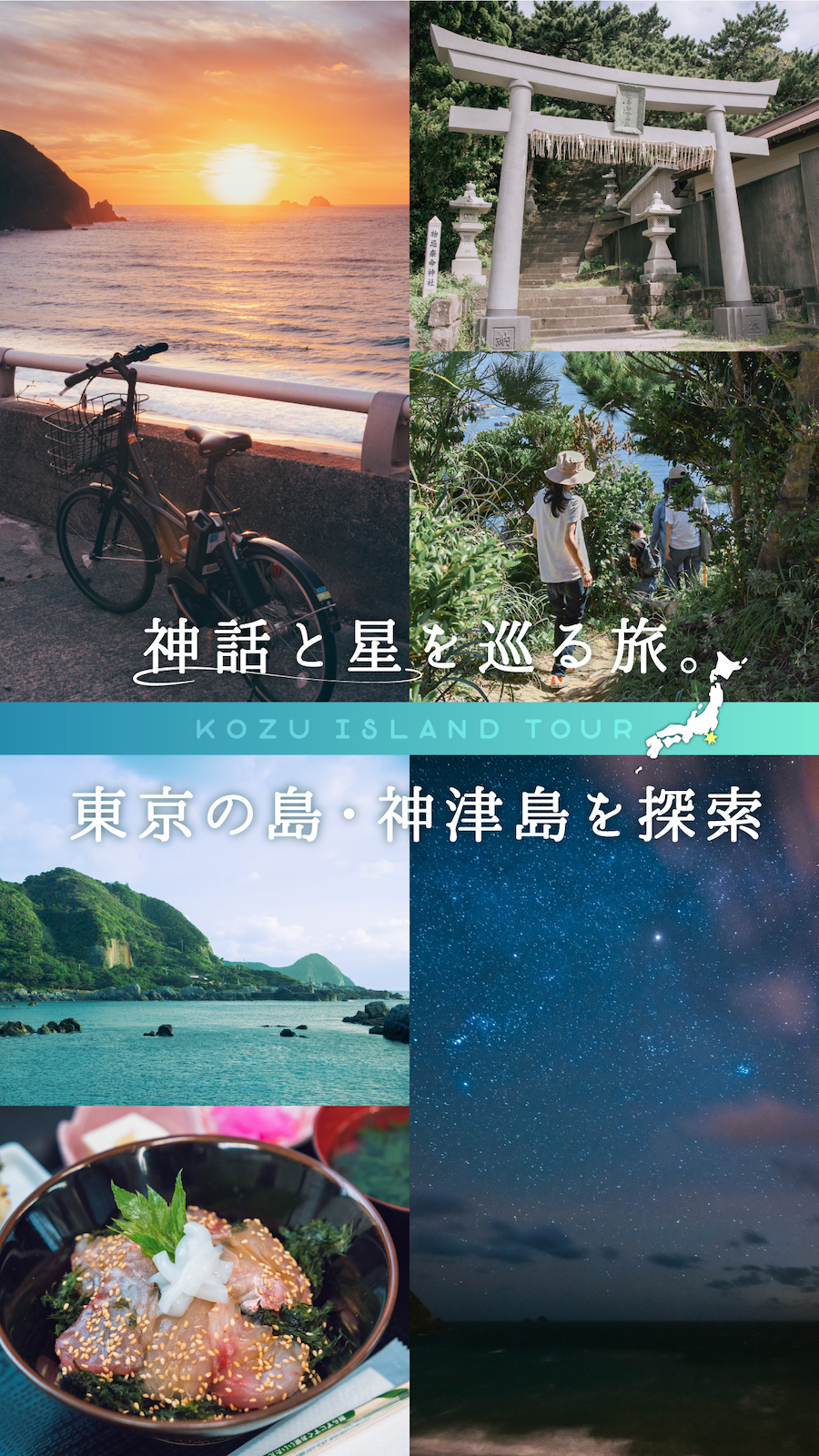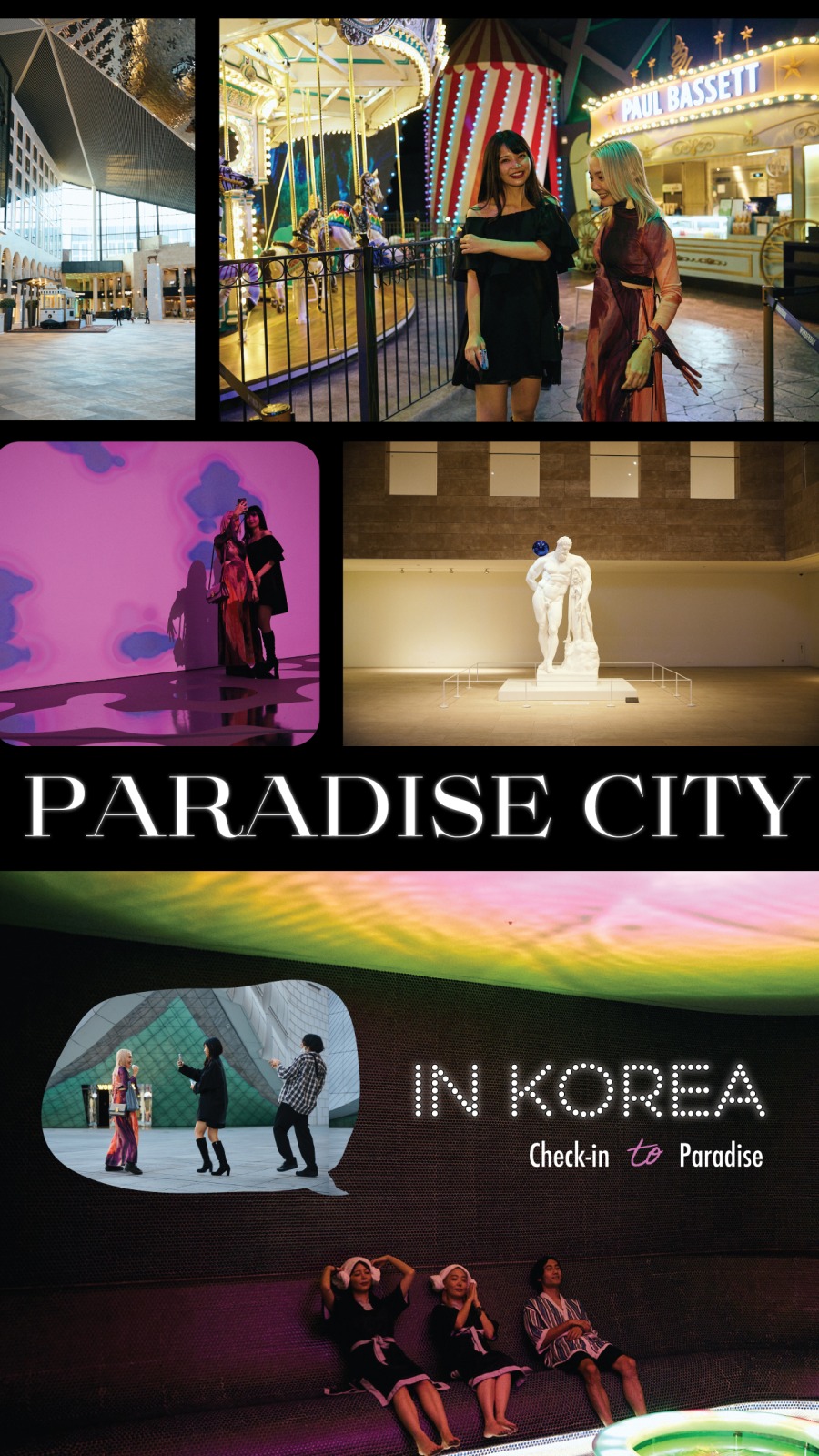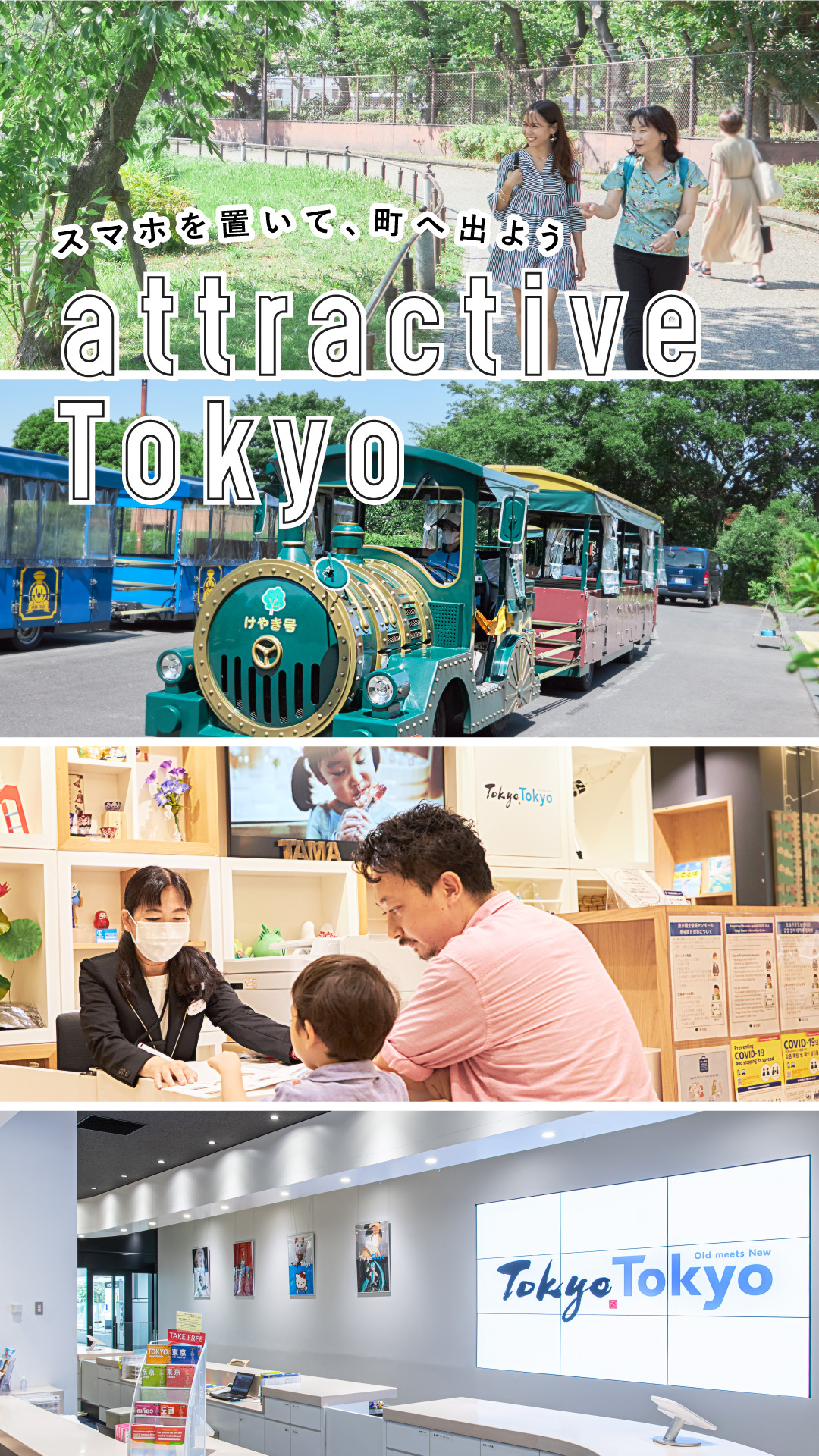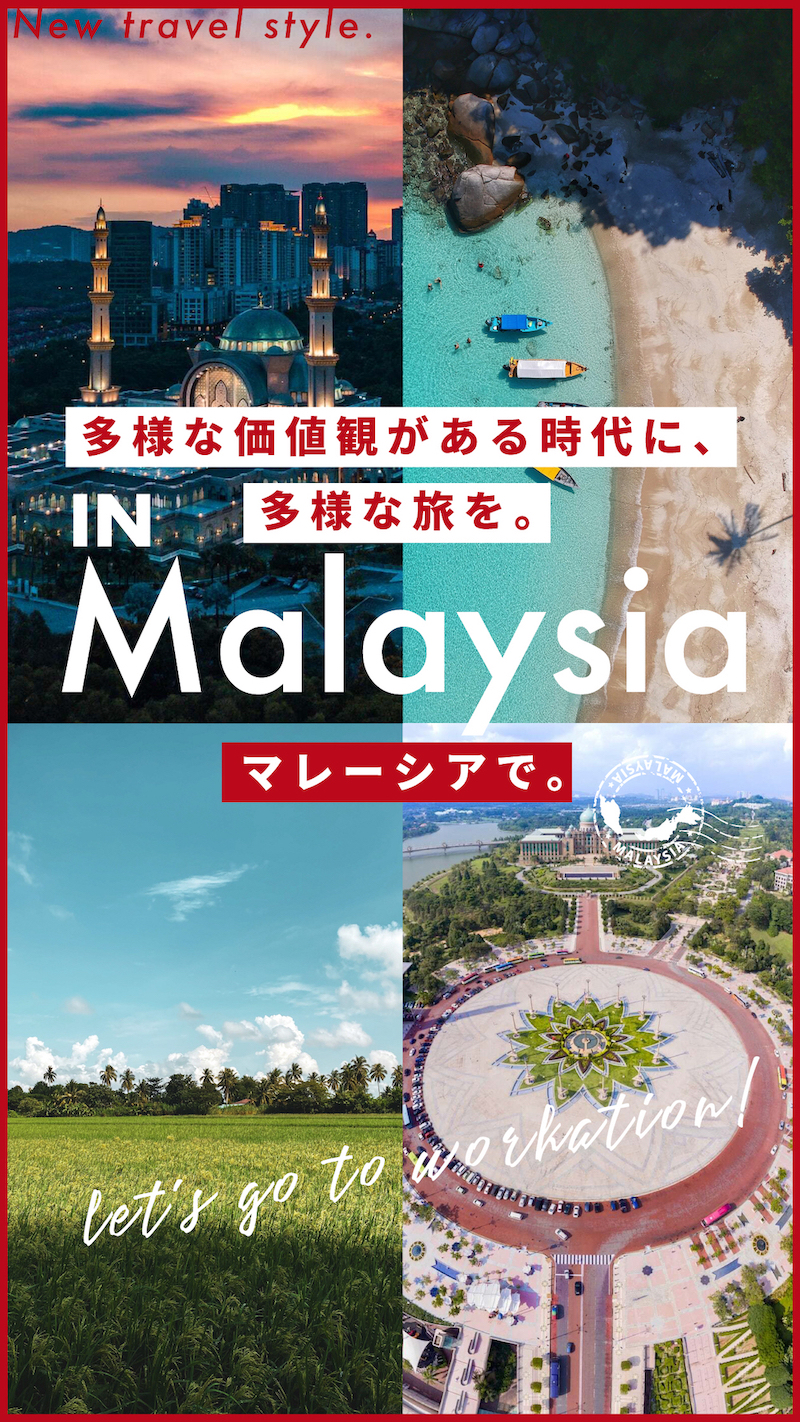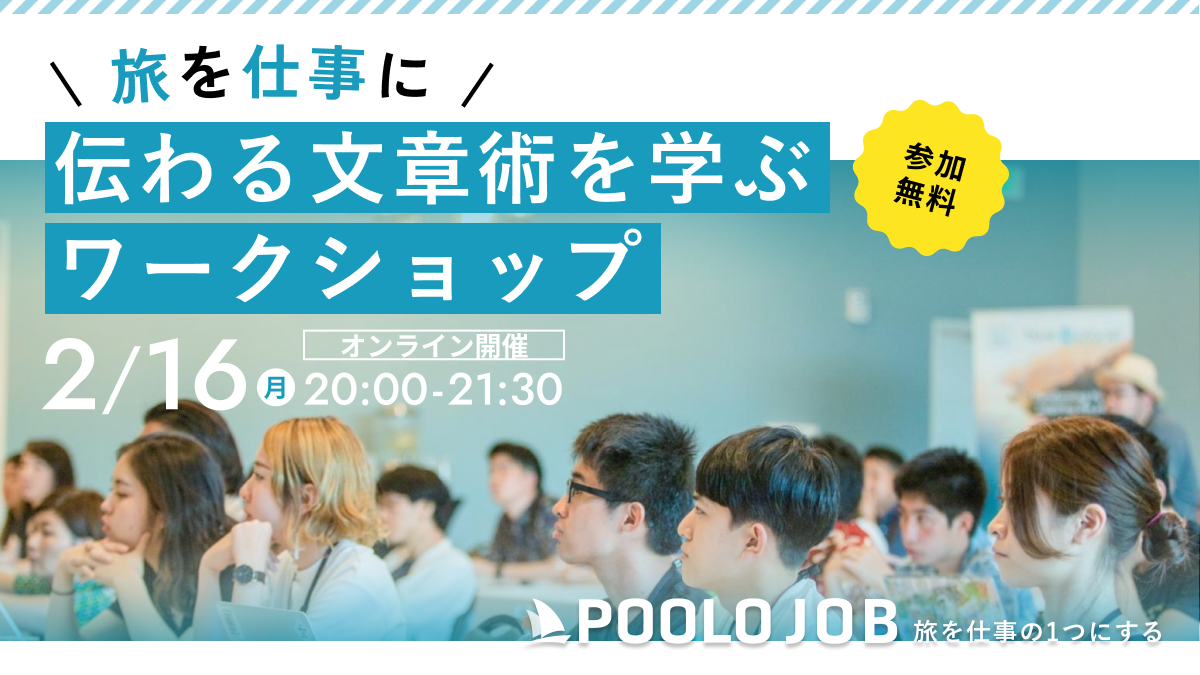異文化との出会いは、いつだって驚きと刺激に満ちている。
だからこそ僕は、単なる観光者として外側から眺めるのではなく、できる限り内側からその世界を見て、感じたいと思っている。
それが現地の文化や人々への最大のリスペクトであり、少しでも理解に近づく道だと信じているからだ。
旅のスタイルは基本的に無計画で、自由気まま。けれど、決して傍若無人に振る舞うわけではない。
むしろ自由だからこそ、その地の空気や時間の流れに身を委ねる。深呼吸をし、胸の中を異国の風で満たし、彼らと同じものを共有する。
そんな旅を大切にしている。
 文化の中に溶け込んで
文化の中に溶け込んで
夕暮れの祈りの中で
昨年、妻と一緒にスリランカを旅したときのこと。
スリランカを代表する世界遺産である、アヌラーダプラの遺跡群。夕暮れどきにその一角にある寺院を訪れると、ちょうど祈りの儀式、プージャの時間だった。
菩提寺・ジャヤスリーマハボディ。ここには、釈迦が悟りを開いたとされるインド・ブッダガヤの菩提樹の分け木が植えられている。仏教を厚く信仰するスリランカの人々にとって、神聖で大切な場所だ。
毎日18時に行われるプージャのために、地元の人々が続々と集まってくる。楽器隊がラッパや太鼓を演奏し始め、人々は仏堂の内外に座り込み、祈りが始まるのを待っている。
僕らもそこに混じって座り込み、邪魔にならないよう、だけどしっかりと参加できる場所で、じっと待った。
 楽器隊が演奏を始める
楽器隊が演奏を始める
やがて僧侶の読経が始まり、後に続いて人々が唱和する。お経には節があり、歌のようだった。僕らも聞き取れる範囲でお経を繰り返し、祈りの唱和の一員となった。
すごい熱気だった。それはスリランカの熱帯気候や、集まってきた人たちの人口密度によるものだけでなく、この地に脈々と受け継がれてきた彼らの純粋で誠実な信仰心が作り出したものだと感じた。
僕は、その熱気の中で、ひたすら胸を震わせていた。
その瞬間、僕らはここに集う人々と、時間と空間、そして心を共有できた気がしたのだ。
もし外から眺めていただけなら、きっとこの感覚は得られなかっただろう。
 人々とともに祈る
人々とともに祈る
時間の流れに合わせて
スリランカでは、時間の流れがゆるやかなことも印象的だった。
ニゴンボという町の海沿いのレストランに入ったときのこと。
カレーのセットを注文したのだが、一向に料理が出てこない。他にお客さんもいないのに、なんでこんなに時間がかかるのだろうか。
1時間後、ようやく料理が運ばれてきた。店員のお兄さんは提供が遅くなったことを謝るわけでもなく、楽しげに僕らに話し掛けてきた。
そしてご飯を食べ終える頃、スマホの画面を見せてきて、「レビューを書いてくれ」と当たり前のように言ってきた。
1時間待たせておいてよく言えるな……。
と思わず苦笑したが、このあとに予定があるわけでもないので、怒ることもせずいいレビューを書くことにした。急いでいるなら「料理はどれくらいかかる?」と聞けばいいだけの話。
それにカレーも本当に美味しかったし、お兄さんがいろいろと話してくれたのも嬉しかった。1時間海を眺めてのんびり待つのも悪くはなかった。スリランカの人にとっては、このゆるやかさと気さくさが普通なのだ。
 美味しかったスリランカカレー
美味しかったスリランカカレー
日本ならば、迅速で効率的な接客が求められることが多い。
だけど、その感覚を異国で押し付けるのは御法度。彼らには彼らの時間の流れがある。
そこに合わせて、楽しむ気持ちを持つことが大切だ。当たり前のことのように思うが、意外とそれを忘れている旅行者を見かけることも多い。
現地の時間や空気の流れに身を任せる。旅のなかでいつも心に留めておきたいことだ。
 レストランのそばの浜辺では、のんびり凧揚げをする人々
レストランのそばの浜辺では、のんびり凧揚げをする人々
インドの旅が教えてくれること
インドでは、電車の遅延が数時間に及ぶこともあるというのは有名な話だが、僕も実際に4、5時間待ったことがある。
そんなときには、駅の中で寝そべってる人々に混じってだらだら過ごすのが一番。文句を言ったところで電車の到着が早まることはないのだから。
みんなの中に溶け込んで寝っ転がっていると、自由で寛大な気持ちになり、この状況を楽しむ余裕さえ出てくる。
 コルカタのハウラージャンクションにて
コルカタのハウラージャンクションにて
また、インド人は「NO」と言わない国民性がある。何かを尋ねられたり、頼まれたときに「わからない」「できない」とは言わず、適当に答えるのだ。
あるカフェに入ったとき、メニューには「コーヒー」としか書いてなかったのだが、これをブラックのアイスで出すことはできるか尋ねたことがあった。
店員は確かにYESと即答したのだが、出てきたのは湯気が立ち込める熱々のホットコーヒー、しかもミルク入りだった。
「アイスって言ったよね?」と聞くと、悪びれることもなく「アイスはないよ」と返された。
その適当さには呆れたが、ここで怒ったところで何も変わらない。受け入れるしかないのだ。僕は「OK」と返事をし、汗を流しながらホットコーヒーを啜った。
 熱々のミルクコーヒー
熱々のミルクコーヒー
これはその店員の人間性というより、インド人の国民性だ(もちろん、店や人によっては事前に断ってくれることもあって、すべてのインド人がそういう訳ではない)。
こんなことはよくあって、たとえば、道を尋ねたら適当な方向を指差されたり、駅で電車のホームの場所を聞いたとき、まったく反対のホームを言われて危うく乗り損ねそうになったり。そんなことがザラにあるのがインドなのだ。
この国民性を否定したり馬鹿にしたりせず、理解の姿勢をとり、そしてどう行動するかを考えることは本当に大事なことだと思う。
道や駅のホームを適当に言うのであれば、複数の人に尋ねてみて、情報を集める。電車が何時間も来ないのなら、来るまでのんびり待てばいいだけ。カフェで「YES」と言われたのにちがうものを出されたら、また別の店で探せばいい。
そんな心構えがインド旅を乗り越える秘訣だし、それは自ずと、他者への理解や許容の心を作り出してくれるものではないだろうか。
 ムンバイの駅。ここで全然ちがうホームに案内された
ムンバイの駅。ここで全然ちがうホームに案内された
異国の風を胸いっぱいに
異文化をできる限り内側から見つめ、理解とリスペクトを示す。
僕は旅には基本的にルールは設けていないが、もしあるとすれば、それだと思う。これはルールというより、行動指針や価値観、心の有りようと言えるかもしれない。
そんな心で参加したアヌラーダプラのプージャで感じた熱気を、僕は一生忘れることはないだろう。
これからもそんな景色を求め、胸いっぱいに異国の風を吸い込み、現地に溶け込みながら旅をしていきたいと思っている。
 一緒に祈りを捧げた、この日のことは忘れないだろう
一緒に祈りを捧げた、この日のことは忘れないだろう
All photos by Satofumi Kimura