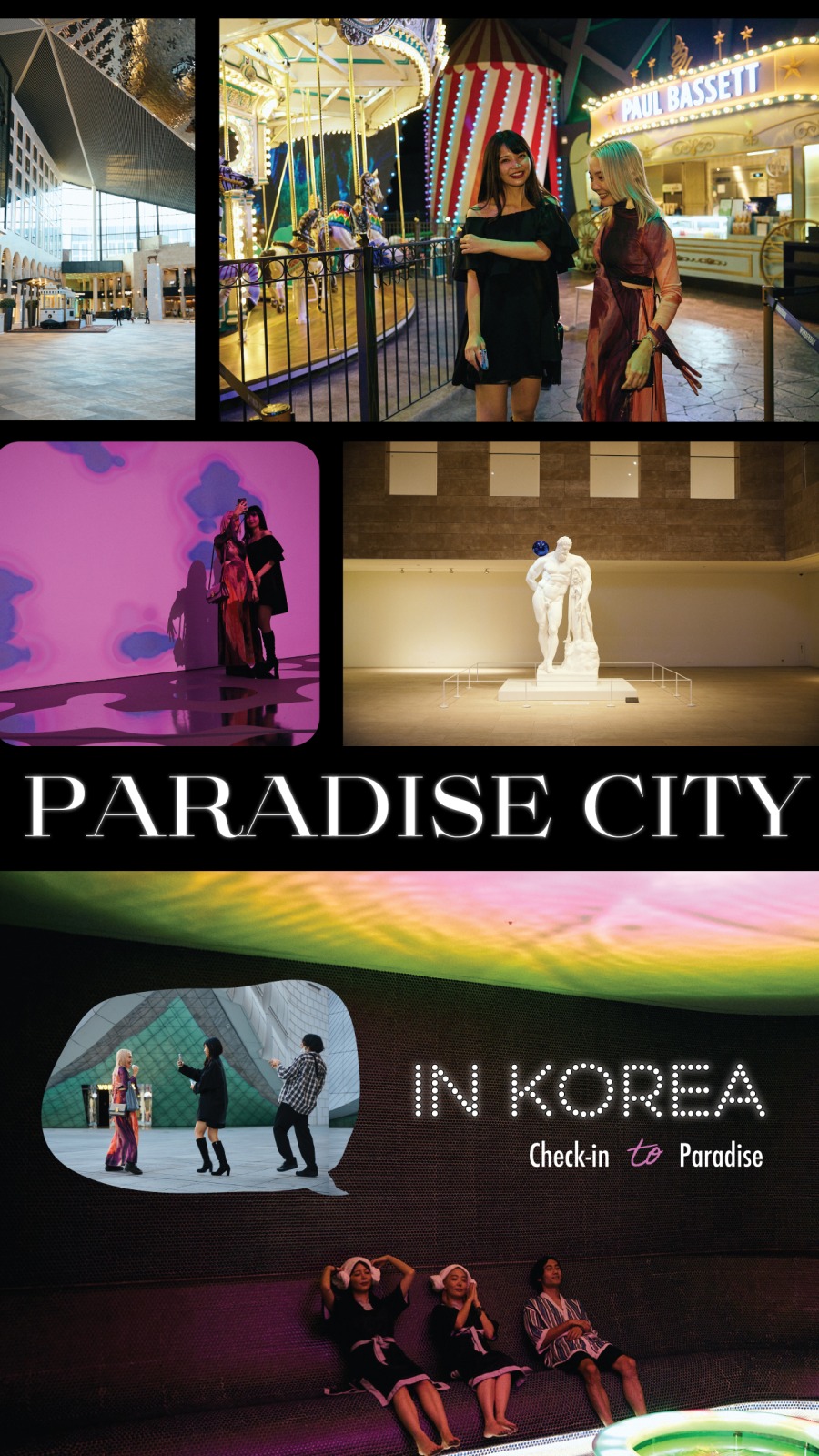別に用事があるわけでもないのに、なぜか何度も戻ってしまう街はないだろうか。
私にとって、それは福岡だ。
私は2016年から2020年まで、福岡で暮らしていた。今は東京に住んでいるが、離れてからも年に一度は必ず足を運んでいる。
街並みなのか、人なのか、空気なのか。それとも、かつての自分を、まだこの街に置いてきたままだからなのか。
もう5年が経ったというのに、いつまでたっても理由はわからないまま。ただ気づけば、また飛行機に乗って向かっている。
ひとついえるのは、福岡が私にとって「始まり」でもあり、同じ瞬間はもう二度と戻らないと知りながらも、それでも何度も訪れてしまう街だということだ。
見出し
第1章:博多区編
飛行機のなかで、もう福岡が始まっていた

早朝の羽田空港
2025年某日。私は東京から福岡へ向かうために、羽田空港にいた。
搭乗時刻ギリギリに飛行機に乗り込んだが、遅刻者が出たらしく、出発は20分遅れ。そのときに、ふと思った——もう福岡は始まっている、と。
出張帰りらしい隣のサラリーマンが、疲れているのか右に左に揺れ、今にもこちらに倒れ込んできそうで落ち着かない。それでも構わなかった。ここから先は、もう福岡なのだから。
離陸してからおよそ2時間。安心して眠ってしまったせいで、目を開けるとコンタクトレンズは渇ききっていた。小窓の外には、すでに福岡の街が広がっている。飛行機は、そのまま街のなかに降りていくようだった。
博多駅|人と熱気が集まる街

博多駅前
「福岡へようこそ」の看板を目にした瞬間、故郷に帰ってきたのだと感じ、張りつめていた緊張が一気にほどけた。
——あぁ、やっぱり私は、この街に戻ってきてしまう。
空港から地下鉄でたった2駅。博多駅に降り立つと、人々の雑踏から空気感が変わるのを感じた。
九州中から集まってきた若者たちの笑顔。スーツケースを引く旅行者、アジアからの観光客。出張で、少し浮き足立ったサラリーマン。この街には、さまざまな思惑が集まってくる。
都会を夢見て、田舎から集まってくる女の子。かつての私だ。仕事も、恋愛も、期待も、不安も。ぜんぶ抱えたまま、この街にやってくる。東京よりも、ずっとわかりやすく雑多だ。
せっかく福岡に来たのだ。まずは食欲を満たしたい。もつ鍋、焼き鳥、餃子……。選択肢はいくらでもある。私が最初に選んだのはラーメンだった。ビールとともに、細麺をすすり、舌鼓を打つ。魚介豚骨の塩気が疲れた体に染み込んだ。

福岡名物・豚骨ラーメン
中洲川端|屋台に残る、2016年の夜

暗闇を灯す屋台の光
2016年。人生が、今よりずっと身軽だったあの頃。私はこの街で、遅れてきた青春を爆発させた。
立ち飲み屋で、たまたま隣にいる人と「どこから来たと?」なんて会話が自然と始まる。お互い名前も知らないまま、ビールから日本酒へ。ただただお酒を酌み交わす。
酔い覚ましも兼ねて、博多にある自宅までひとりで歩いて帰ったこともあった。ときには朝焼けが綺麗に見える日も。
川沿いに並ぶ中洲の屋台は、今も変わらずそこにあった。初めて屋台に連れて行ってくれた年の離れた友人。コミュニティのゲストとして来ていたお兄さん。3人でビール片手に、夢や希望を語り合ったあの夜を今でもはっきり覚えている。
福岡の街中を歩くたび、あの日々の記憶が、次々に蘇る。と同時に、胸の奥に、小さな引っかかりのような「しこり」が残っていることに気づく。
あれから10年。ときは流れ、私も、周りも変わった。それなのに、自分だけが変わらず、取り残されたような気持ちになる。あの頃の新鮮な情熱やときめき、そして同じ時間は戻らないとわかっていながら、それでもなぜまた求めてしまうのだろうか。