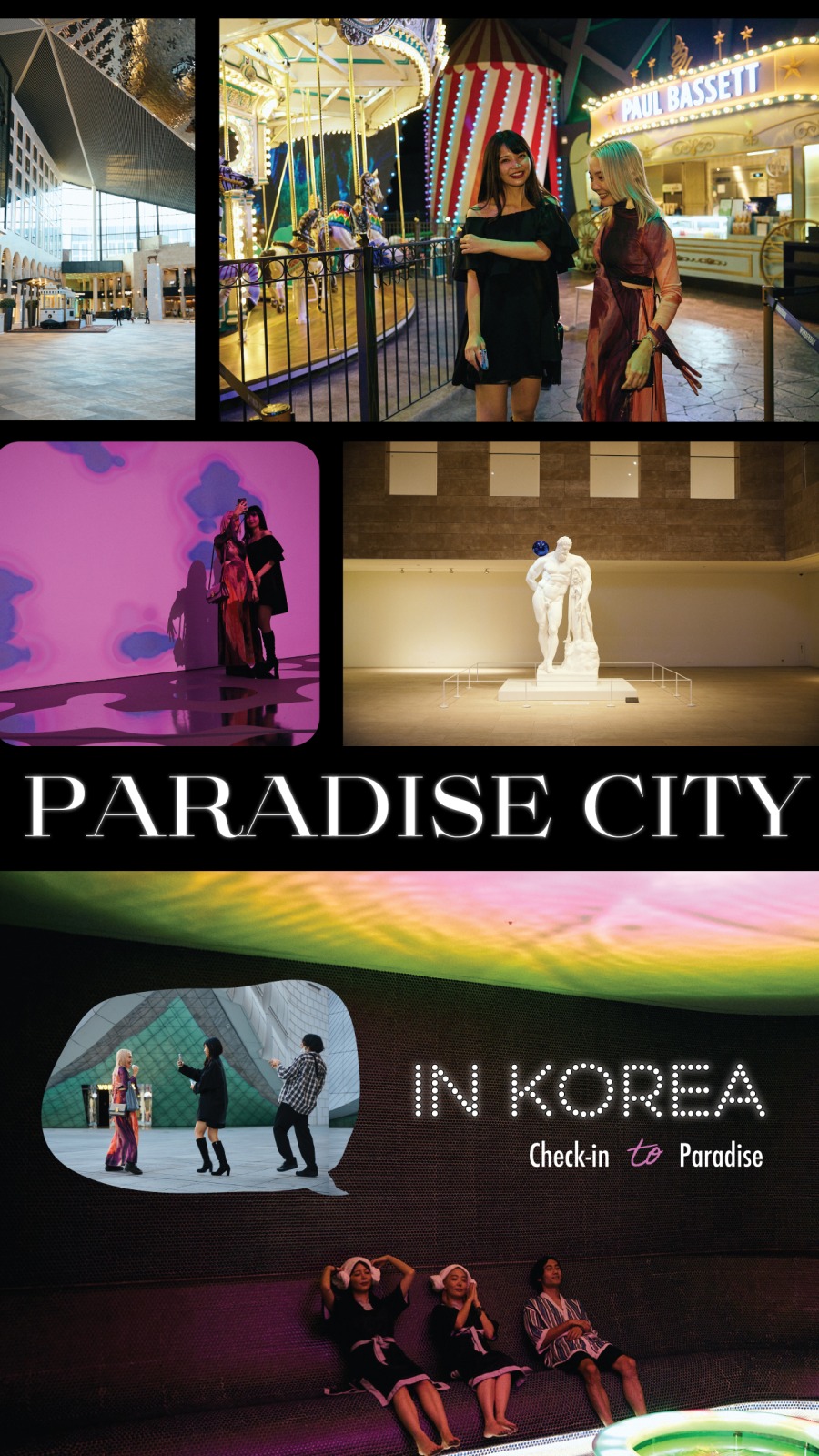東京に来て4年。 視界を埋め尽くすデジタル広告、手元に目線を落とし足早に歩いていく無数の人々。そんな「都会の景色」の一部になることにも慣れ、今では渋谷の雑踏さえも無心で駆け抜けることができます。
けれど、その適応と引き換えに、僕は社会人としての「こうでなくてはいけない」というレッテルを、強く握りしめて生きるようになっていました。
自分の身体がいつから強張っていたのかさえ、わからなくなっていたある日。 凝り固まった心を優しくほどいてくれる場所に出会いました。長野県にある、わずか人口800人弱の村「根羽村」です。
東京からのアクセスは決していいとは言い難いにも関わらず、移住、もしくは二拠点生活にしてでも住みたいと思ってしまうほど居心地の良い「根羽村」。その魅力を本記事ではご紹介します。
見出し
森と生きる根羽村の人々

根羽村は長野県の南西部最南端に位置する人口800人に満たないほどの小さな村です。
総面積の92%が森林である根羽村では、村の全世帯が山持ちで、行政と民間が一体となって森林組合を経営して森林の保全に力を注いでいます。
まさに根羽村のコンセプト通り森とともに生き、よりしあわせな人生を歩もう。」を体現しているのが根羽村の方々です。
つながりがあふれる村へ。
森とともに生き、よりしあわせな人生を歩もう。
根羽村には「ネバーギブアップ宣言 2.0」という宣言があります。全村民にインタビューを実施し、村民の声をもとに作られたこの宣言には20年後の村の理想像が詰め込まれています。そして「ネバーギブアップ宣言2.0」の基本構想の中にある一つが「つながりがあふれる根羽村」。
根羽村は村内外の様々なコミュニティとの交流やつながりを大切にし、 「つながりがあふれる」 村を目指していこうという考えです。
そんな根羽村へは自然を堪能する目的として訪れることはもちろん、お試し移住もおすすめです。日頃から村の人以外とのつながりを大切にしている根羽村の人は外から訪れた人々を、驚くほど自然に日常生活の中へあたたかく迎え入れてくれます。
根羽村の日常、生活を体験させてくれる「宿」
「村暮らし」を体験する【まつや邸】

2泊3日以上のおだやかな「村暮らし体験」をしたい方におすすめな一棟貸しの宿「まつや邸」。築130年の古民家を改装したこの宿は郵便局として村の人々が集う場所でもあったそう。
累計200名の村内外の方々がリノベーションに関わってできた「まつや邸」はまさに根羽村の想いが込められた宿の一つです。

滞在期間中の行程は村民でありオーナーである杉山さんに相談するのがおすすめ。どんな根羽村暮らしを体験してみたいか、を伝えると林業、農業、山菜、竹のこ採り、渓流釣り……季節に応じて様々な村の日常に潜むコンテンツを体験させてくれるはず。

プランは「村暮らし体験プラン (2泊~4泊)」、「村暮らし長期滞在プラン(5泊以上〜)」の2種類。
自分にあったプランを選択して「村暮らし体験」を満喫してみてください。
根羽村での長期滞在にピッタリな【トライアルシェアハウス】

長期滞在向け、根羽で「新しい暮らしを始めたい人」におすすめなのが「トライアルシェアハウス(お試し住宅)」。
根羽村内での就業・移住・起業に挑戦したい人が気軽に滞在できる場をつくりたいという想いからできたこのシェアハウス。これもまさに「ネバーギブアップ宣言 2.0」、「挑戦と応援がかけ合わさる根羽村」が体現されています。
この「トライアルシェアハウス」は地域の木材を使用している新築物件。玄関を開けて中に入ると根羽の木々に全身を包み込まれるような気がします。

今回の根羽村での滞在では、この「トライアルシェアハウス」に4泊しました。数年前から「暮らすように旅をする、旅するように暮らす」をテーマに考えている僕にとって、ここでの滞在はまさに「根羽村での暮らし」を体験することができました。
身体で感じる森の循環。「根羽の森と生きる」を体験する

わずか数泊でも「村の日常」に身を置いていると、不思議と人との縁も繋がっていくのが根羽村の魅力。 滞在中に知り合った村人・幸山(こうざん)さんのご厚意で、所有する山へ案内していただくことに。
幸山さんが経営する「ハッピーマウンテン」では「牛らしく 人らしく あるがまま」をコンセプトに、林野に牛を放ち飼育する「林間放牧」を導入しています。そのため365日、どの季節、いつ訪れても自然で生きる牛たちに会うことができます。
「ちょっと手伝ってくれるか?」 そう言われて始まったのは、その日の朝に切り出されたばかりの丸太を運搬する作業。
 軍手をはめ、まだ樹皮が湿っている木を抱え上げる。ズシリとした重みが腕に伝わると同時に、切り口からフワッと強烈な、でもどこか懐かしい木の香りが立ち上ります。長らく嗅いでいなかった、生きている森の匂いに肺が喜んでいる気がしてきます。
軍手をはめ、まだ樹皮が湿っている木を抱え上げる。ズシリとした重みが腕に伝わると同時に、切り口からフワッと強烈な、でもどこか懐かしい木の香りが立ち上ります。長らく嗅いでいなかった、生きている森の匂いに肺が喜んでいる気がしてきます。
 足場の悪い斜面を踏みしめながら、無心で木を運び続ける。 ふと作業の手を止めて自分を見下ろすと、ズボンの裾は土で茶色く汚れ、上着の背中には枯れ葉がいくつもくっついていました。
足場の悪い斜面を踏みしめながら、無心で木を運び続ける。 ふと作業の手を止めて自分を見下ろすと、ズボンの裾は土で茶色く汚れ、上着の背中には枯れ葉がいくつもくっついていました。
その汚れさえも愛おしく感じるので不思議です。東京のような都会にいると味わうことのない、土の感触と森の匂い。 都心に暮らすことで少しずつ凝り固まっていた心が、久しぶりに自然と触れ合うことによってほどけていく感覚に包まれます。
根羽村の面積の9割以上は森林。 この村の人々は、こうして何世代にもわたって山に入り、木を植え、育て、切り出し、そしてまた植えるというサイクルの中で生きてきました。

僕がこの日に運んだ丸太は、この壮大な循環のほんの一部に過ぎない。けれど、その重みを身体で感じ、服を泥だらけにした瞬間、ただ美しく見えていただけの根羽の森が少しだけ、自分もその一部としてともに生きているような感覚になりました。
汗をかき、泥に汚れながらその土地の生活、日々の循環に参加させてもらうこと。想像以上に力仕事で数日間の筋肉痛になってしまいましたが、これまで体験してきたどんなアクティビティよりも深く、心に刻まれる体験となりました。
人々が集う根羽の新拠点「シラネバ」

元々旅館だった木造2階建ての空き家を改修してつくられた、根羽村の新たな拠点「シラネバ」。
地域おこし協力隊の白根拓実さんが村民と協力して作ったこの場所は根羽村を訪れる人が地域に触れ、地元の人たちとも交流できる場にしたいという思いが込められています。

「シラネバ」という名前は、彼の苗字である「白根」と「根羽」を掛け合わせたものであり、「根羽村を知らねば」という想いや、これから何かが生まれていく「Never ending」な可能性も含んでいるのかもしれません。

すでにシラネバは喫茶・本屋・セレクトショップ・不動産事務所が一体になった複合的施設になっているにもかかわらず、白根さんいわく「まだ未完成」とのこと。
根羽で暮らし、「シラネバ」の完成へ向けて悩み、笑い、試行錯誤している白根さんの姿は、訪れる僕に「君はどう生きるの?」と優しく問いかけてくるようでした。
一緒に「シラネバ」内で作業や話をしているうちに白根さんや施設に訪れる人々との距離が縮まっていきます。

彼のような若い世代が、この土地の風土にしなやかに根を張り、新しい風を吹かせている姿を見て、勇気と元気をもらいます。
根羽に滞在し、根羽に住む人々と交流をしていると、すっかり忘れてしまっていた人との距離感を思い出します。そして滞在の日数を重ねるうちに心がほどけていく感覚に包まれます。都会で肩肘を張っているだけでは得られない「何か」を確実に得ている感覚がありました。
偶然の縁が招いてくれた、熱狂のモルック大会

根羽村に滞在している間に偶然開催された第一回「根羽村 モルック大会」。
村内にある、使われなくなった施設を活用した取り組みとして、開催されることが決まったこの大会に、根羽村の方にお誘いいただき参加しました。
根羽村は定期的に村民企画の様々なイベントが開催されているのだとか。訪れた際には、村の方とお話しをして、聞いてみても良いかもしれません。「何かイベントがあったりしますか?」と。

初めての開催とのことでしたが、地元の方々が集まり、和気藹々とした、温かく平和な空気感が流れていました。フィンランド発祥のスポーツ、モルック。木材を資源とする根羽村との親和性を感じます。
「ナイスショット!」「あー、惜しい!」 木の棒が倒れる軽快な音と、弾けるような笑い声。 名前も知らなかった人たちとハイタッチを交わすうちに、いつの間にか「観光客」という肩書きが外れ、ひとりのプレイヤーとしてその場に溶け込んでいくのを感じました。
ルールもよく知らない状態での参加でしたが、チームを組んだ皆さんは、昨日会ったばかりの僕を「新しい仲間」として当然のように輪の中へ迎え入れてくれました。
過ごす日数が長くなるほど、訪れた人を自然に受け入れていく根羽の人たちの懐の深さに魅了されていきます。
旅の終わりに

昨今、よく耳にする「サステイナブルツーリズム」や「関係人口」といった言葉。 今回の旅で、僕はそれらの言葉を頭で理解するのではなく、身体で感じることができた気がします。
別れ際、地元の方が投げかけてくれた「また来てください」ではなく、「また帰っておいで」という言葉。 そこには、観光客と受け入れ側という境界線はなく、同じ時間を共有し、一緒に汗を流した人同士の温もりがありました。
これからの時代、僕たちが求める旅のスタイル。 それは、名所を巡るスタンプラリーのような旅ではなく、その土地の風土や、そこで生きる人々の営みに、自分自身の感性をチューニングする「共鳴」する旅なのかもしれません。

東京に戻り、また渋谷のスクランブル交差点を歩く日々が始まりました。 相変わらず、頭上には無数のデジタル広告が明滅し、巨大な鉄の塊から吐き出された人々が、それぞれの目的地へと急ぎ足で向かっています。
けれど、以前と少しだけ違うのは、僕の足取りがほんの少し軽くなったこと。そして、心の中に「根羽村」という、いつでも帰れる静かな場所があるという、絶対的な安心感です。
Photos by Ryuo Ikeda, Tatsuya Kanabe, Misako Yoshida