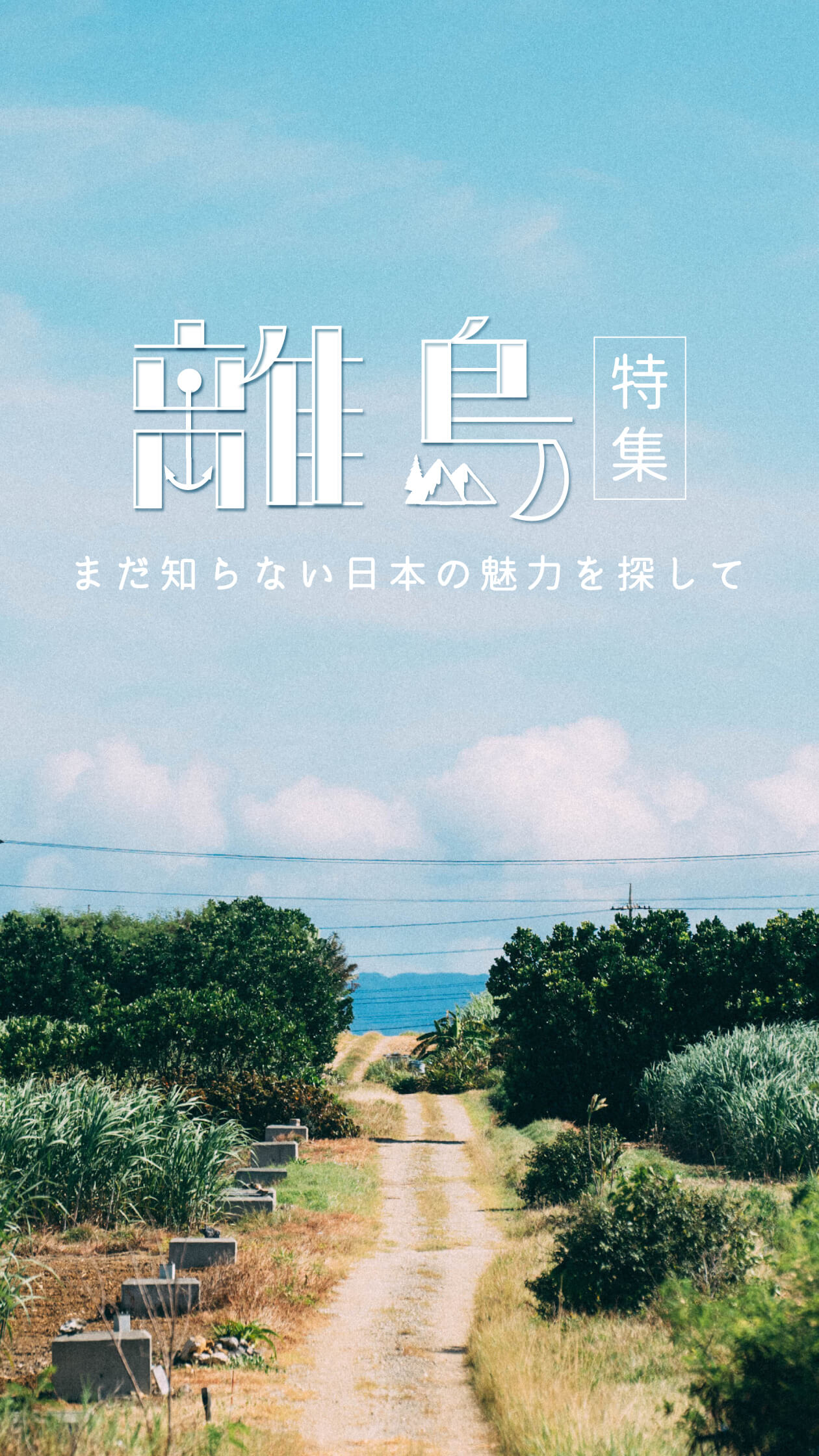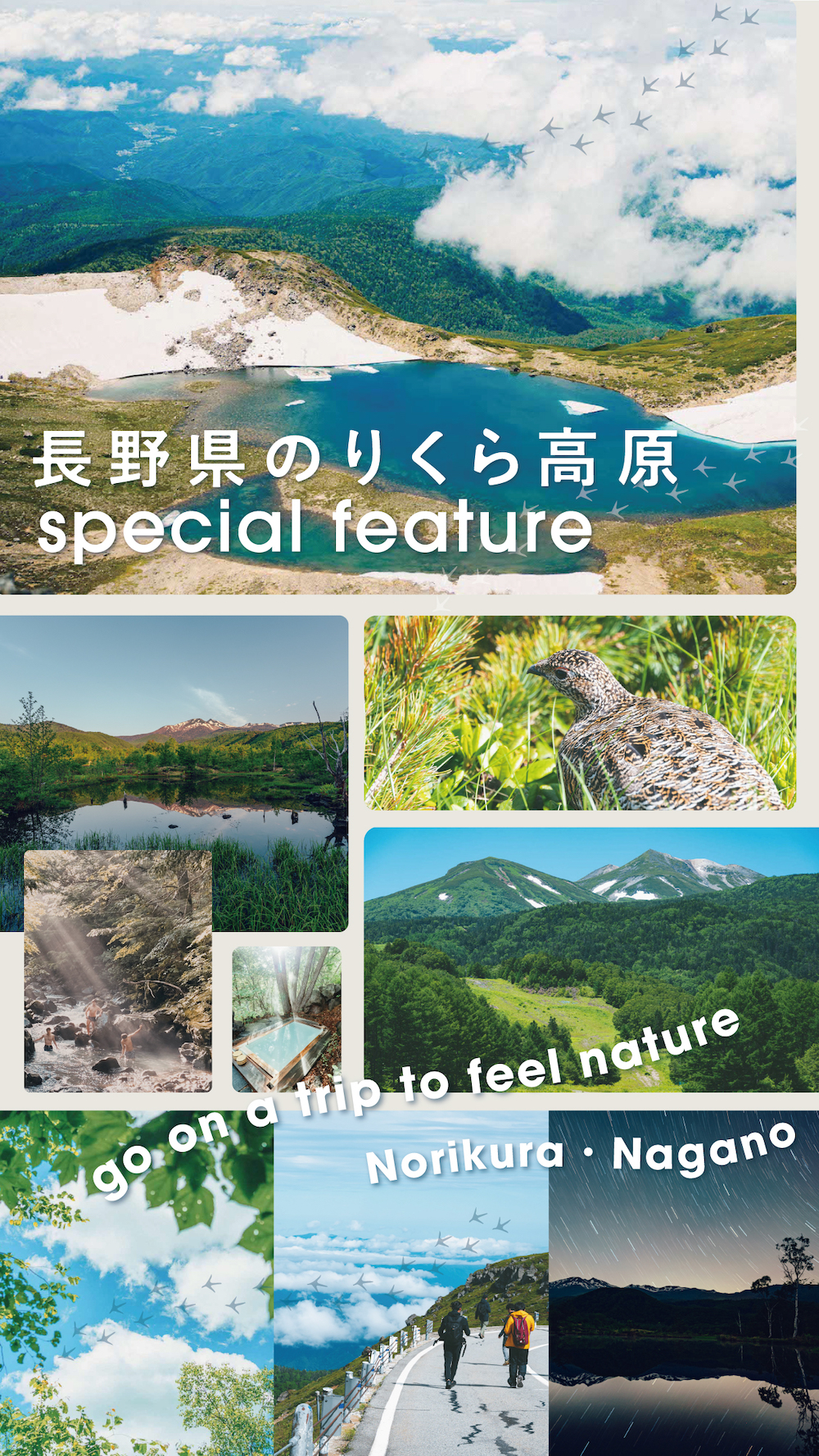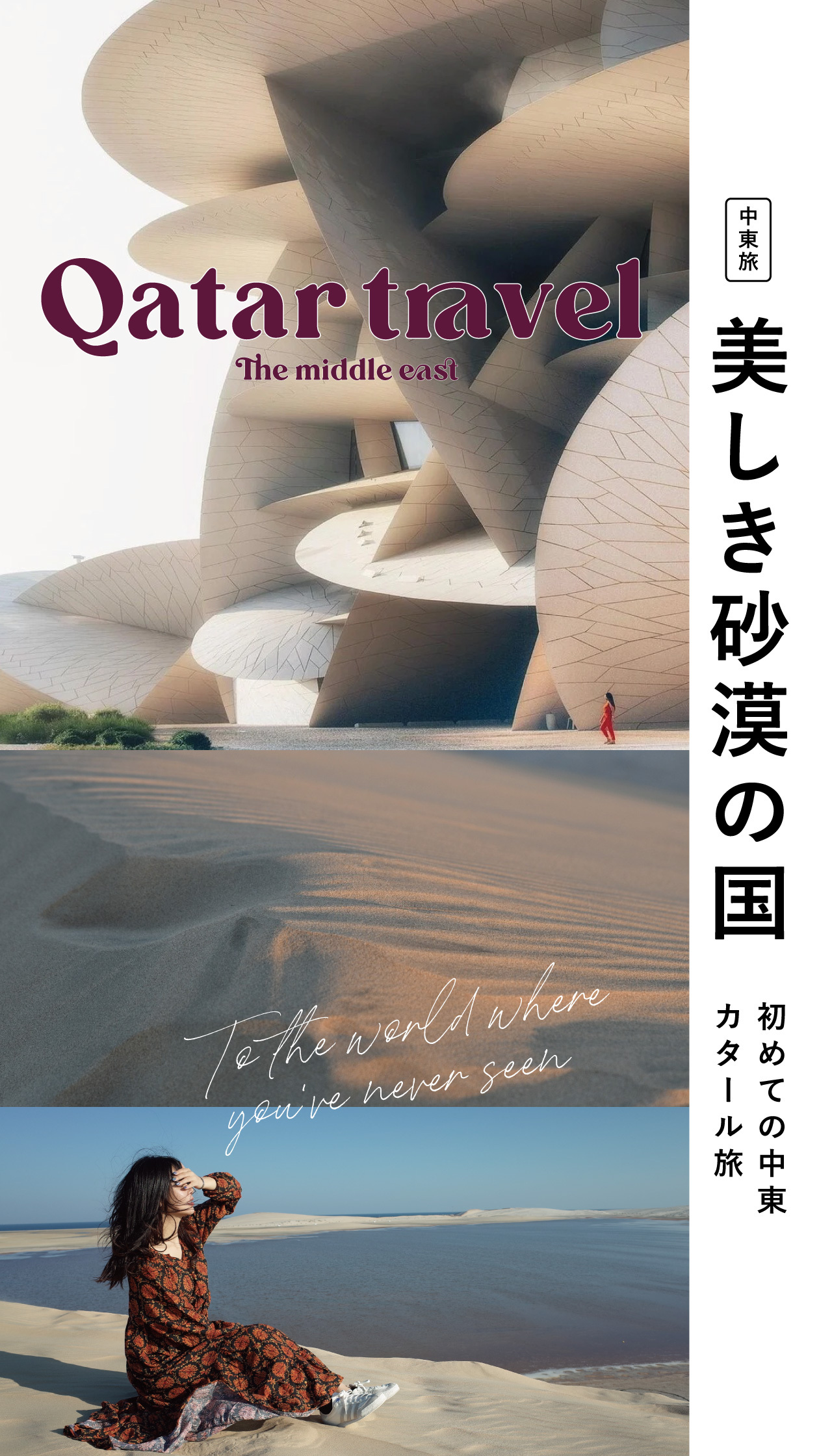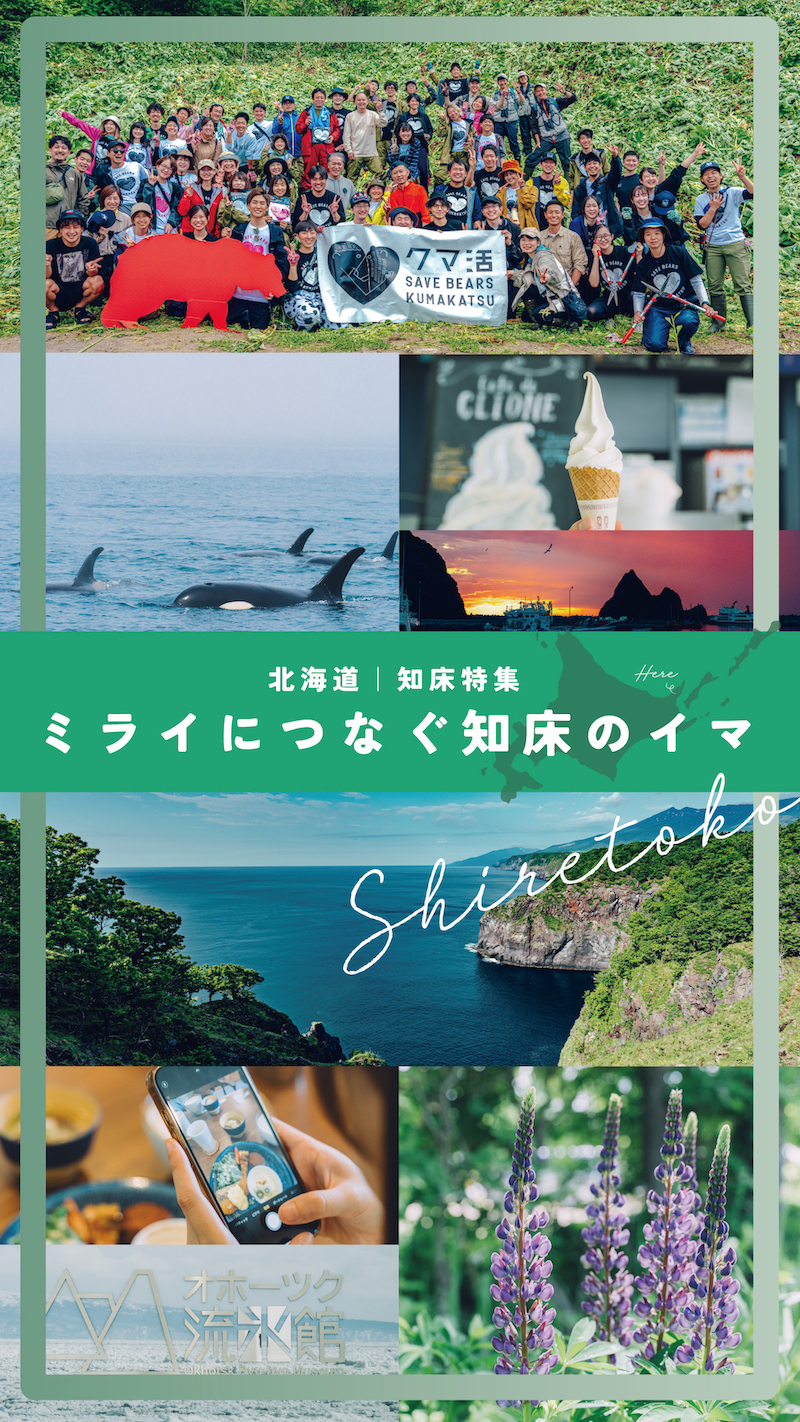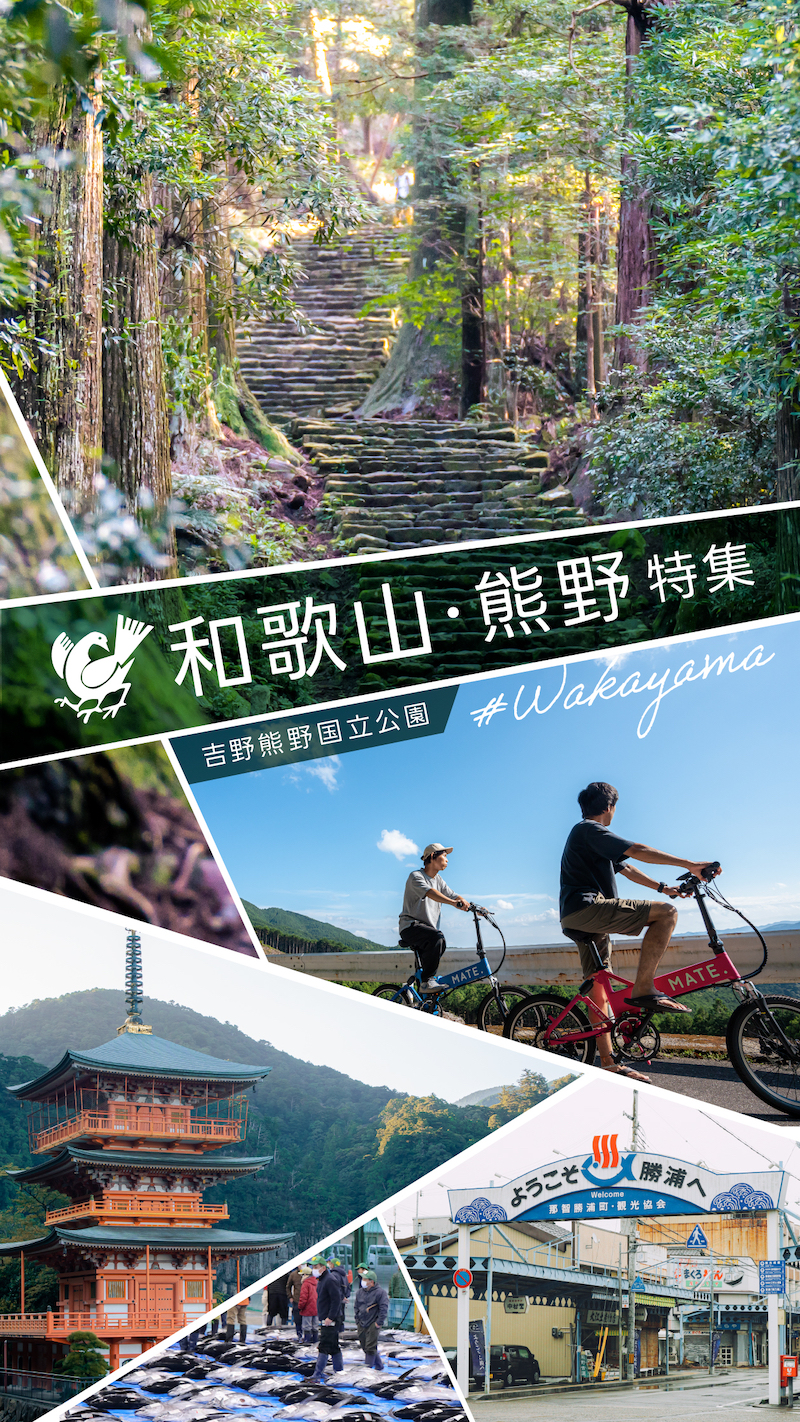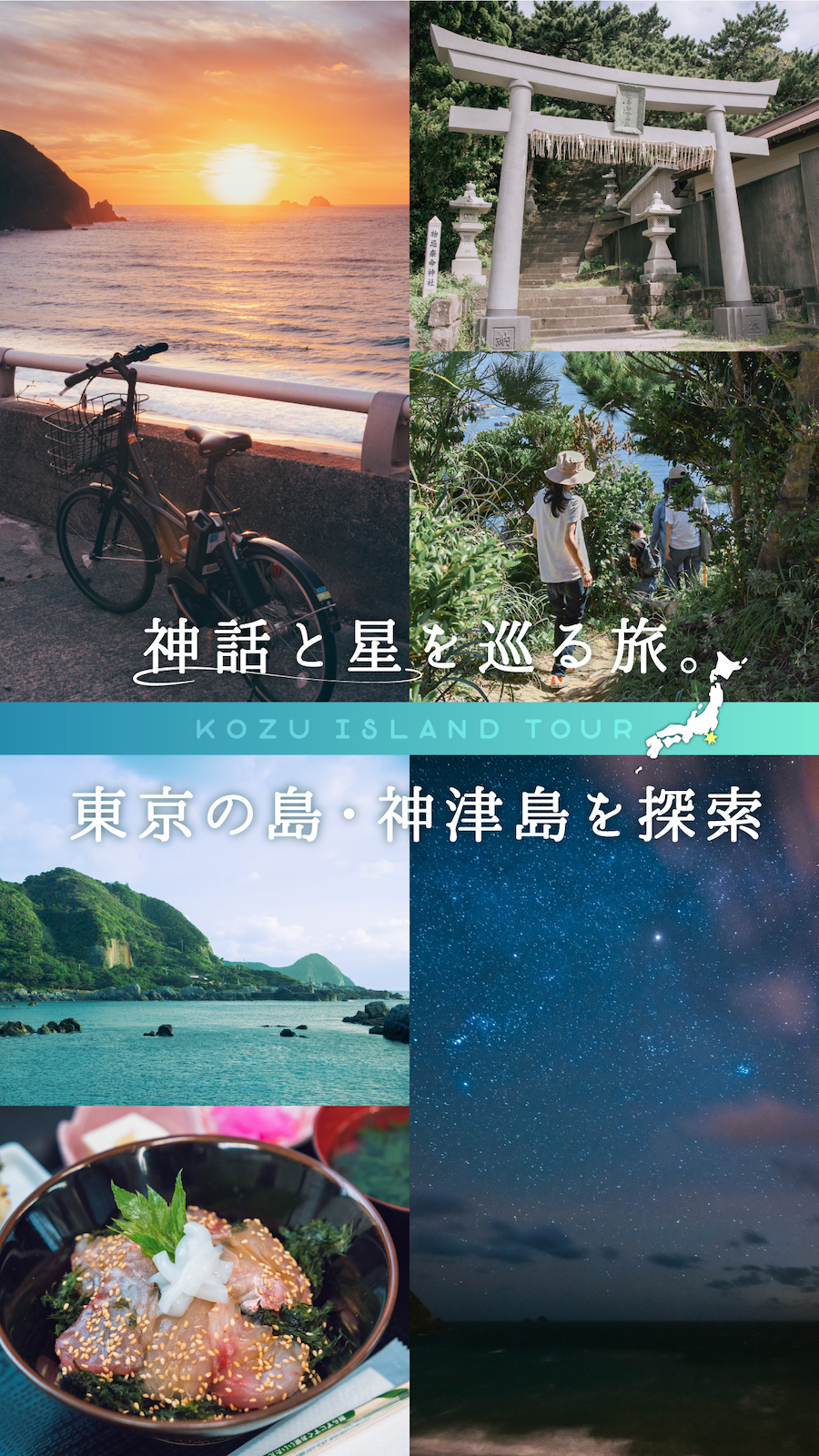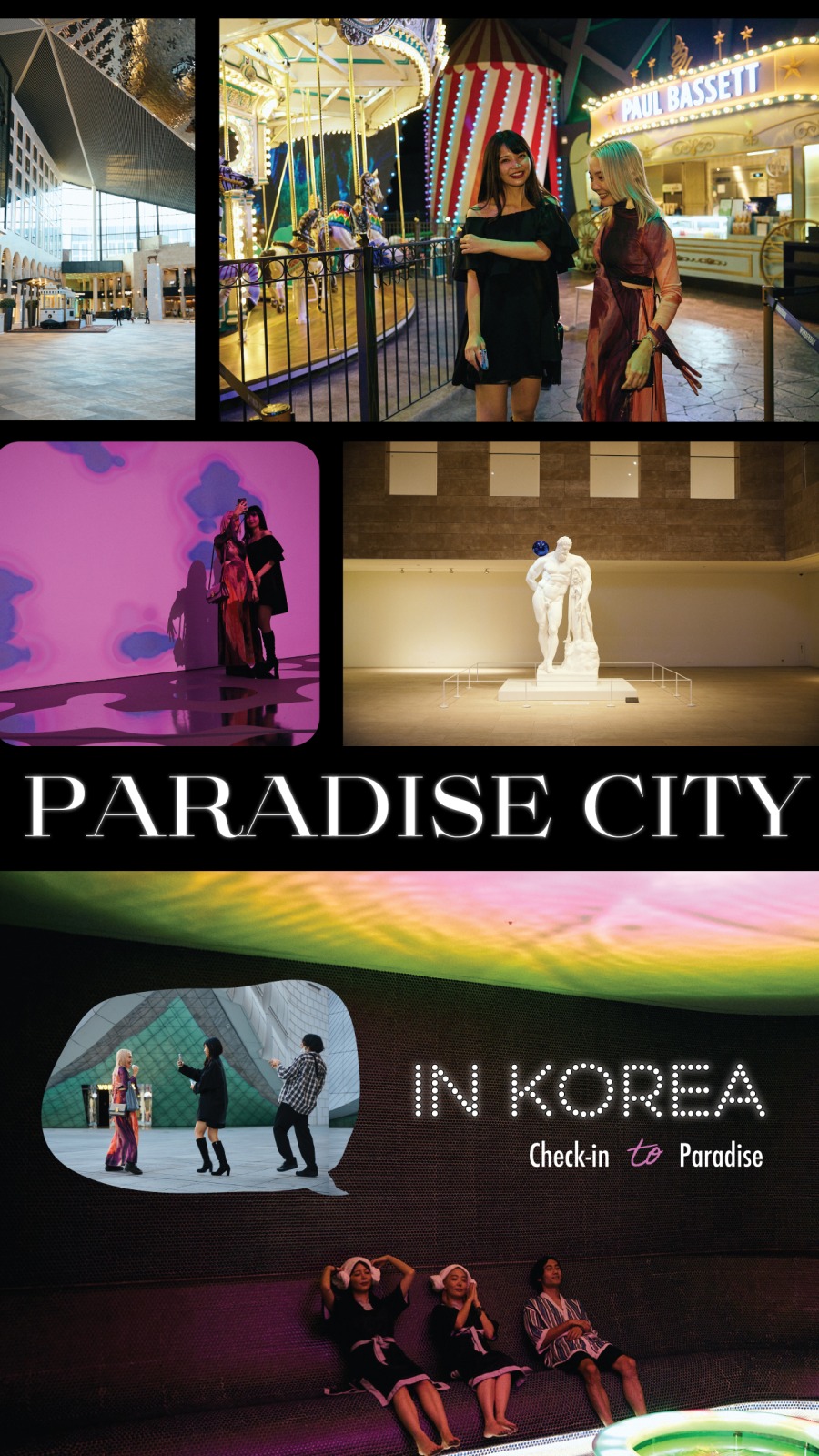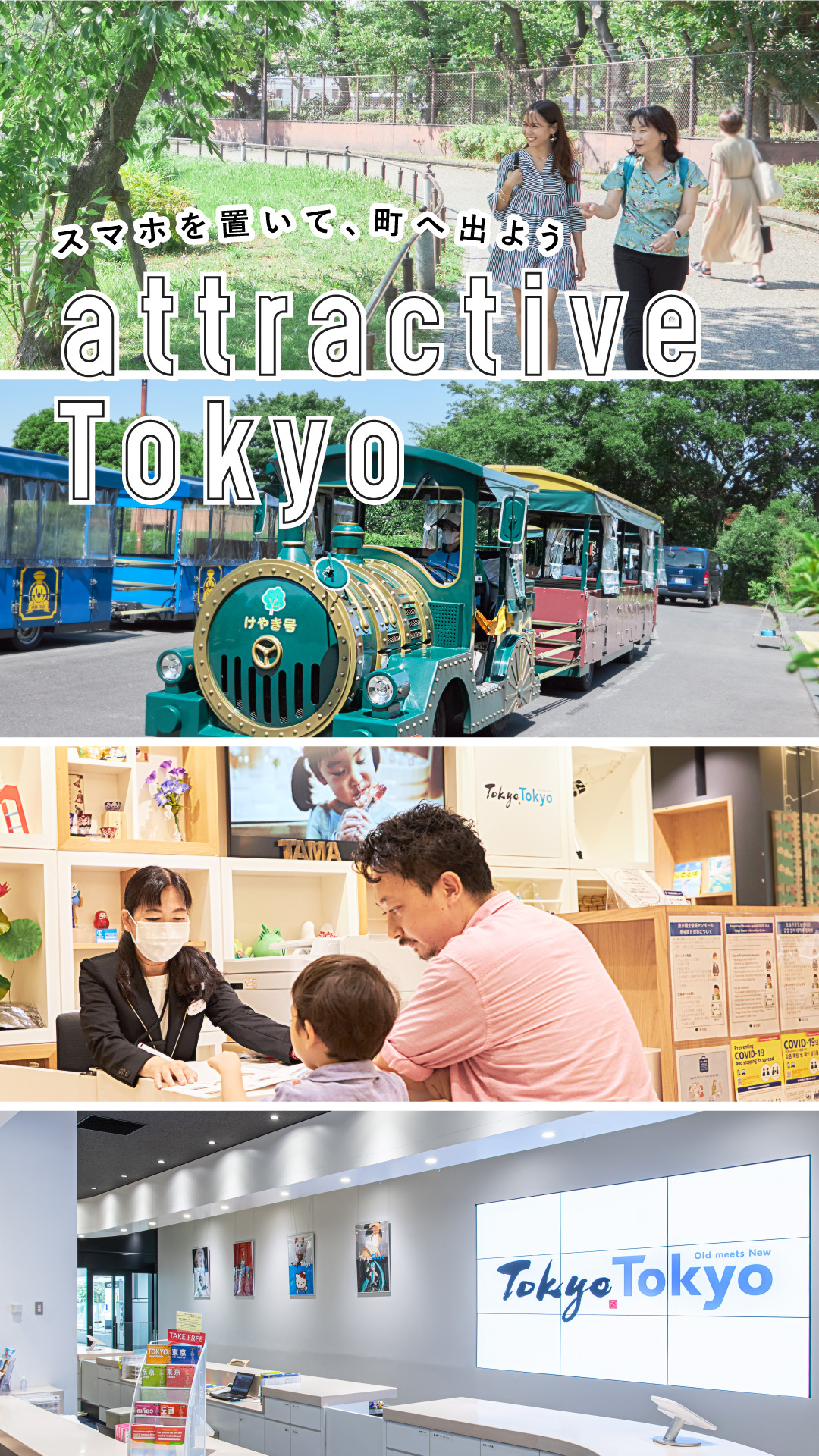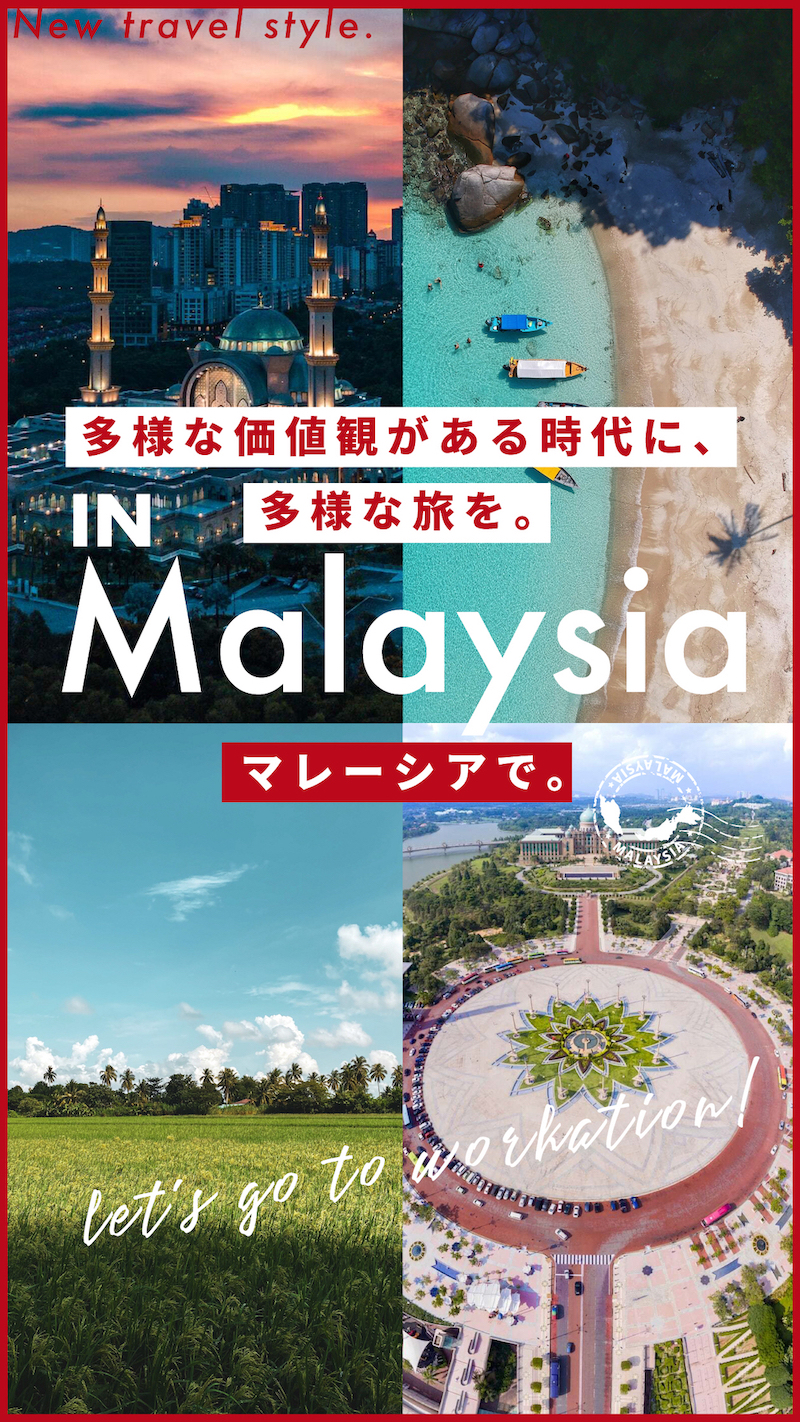カリブ海に浮かぶキューバ ━━
青い海と柔らかな光の太陽、時間がゆったりと流れる島国。旧市街の石畳を走るクラシックカー、色褪せたコロニアル建築、どこか社会主義の空気を感じさせる街並み。壁には革命家チェ・ゲバラの肖像が見え隠れし、歴史と日常が静かに重なっている。
ここは、アーネスト・ヘミングウェイが愛し、物語を紡いだ国。ハバナの街角で酒を傾け、コヒマル(ハバナ近郊にある漁村)で漁師と交わりながら小説を書いた彼の足跡は、まるで今も島の空気に残っているかのよう。
けれどわたしの旅には、彼の物語を追うのではなく、自分だけの物語を見つけるための“マイルール”がある。

━━ 目の前の出来事を、その向こう側まで想像してみること。
例えば、スペイン語圏であるこの国で、英語を母語としない現地の人々と旅行者たちがつたない英語で会話するとき、言葉にできなかった想いがどこかに残っていないかを考える。
暮らしのなかで当たり前に祈る人を見ながら、わたしにとっての祈りとその人にとっての祈りは、同じなのか、それともまったく違うものなのかを想像する。
2019年8月、私はそんなふうにキューバを歩いた。観光名所をめぐるよりも、その瞬間に広がる「誰かの人生の奥行き」を想像することで、旅がより深く、自分自身の物語へと変わっていく。世界の見え方が広がっていく。
心に浮かぶ花を集めよう

当時大学生だったわたしにとって、旅先での宿探しはいつも小さな冒険だった。特にキューバでは、限られた予算に加え、情報のなさに振り回されながら、路地裏を歩き回った。インターネットでの情報も少なく、電波のないキューバでは、スマートフォンは全く役に立たない。現地でその日の宿を歩いて探した。
ハバナの街を歩き、建物の壁に掲げられた「Casa(カーサ)」の小さな看板を見つけるたびに、息を潜めて中を覗く(Casaとは、日本でいう民泊のようなもので、アパートの一室や、自宅の一部を旅人へ提供する宿が街のいたるところに存在しているのだ)。
覗いた先に映るのは、タイル張りの床に、洗濯物が風に揺れる屋上、子どもたちの声、そして掃き清められた路地。ただ宿を見つけるだけではなく、そこに暮らす人たちの時間の流れや、小さな営みに自然と目を向けている自分に気づく。
路地を曲がるたびに、新しい表情の街が現れる。情報がないからこそ、道に迷い、立ち止まり、周囲を観察する時間が増える。その瞬間瞬間に、目の前にある出来事の向こう側。
“誰かの人生や想い”を想像することが、わたしのマイルールを実践する時間でもあった。

海沿いの路地を曲がると、子どもたちが手招きをしてきた。スペイン語以外はまったく話せない彼らは、ただ手を振りながら笑顔で「子犬がいるんだよ!」と身ぶりで教えてくれた。異国で子どもたちに話しかけられた瞬間に、一瞬でも悪い予感を働かせてしまった自分がなんとも恥ずかしかったのを覚えている。
その瞬間、言葉は必要なかった。小さな路地の隅で丸まる子犬を見せたくて、ただ純粋に嬉しそうに伝えたい――その気持ちが、わたしの胸にまっすぐ届く。わたしも「とっても愛らしいね、話しかけてくれてありがとう」という想いを、言葉以外のなにかで全力で伝えた。
こんなやりとりのなかで、互いに気持ちがきちんと伝わる感覚があると、あたたかい気持ちになる。相手と自分の心のなかに、ちゃんと同じ花が浮かんでいる感覚。このお花を集めることが、旅の醍醐味のひとつなのかもしれない。
祈りが結ぶもの

薄明かりのハバナを歩いていると、小さな教会の前で足を止めた。扉の隙間からこぼれる光の中、人々は静かに祈りを捧げている。白い衣をまとった信徒たちが、ろうそくや色鮮やかな供物を祭壇に並べ、香炉の煙がゆっくりと立ちのぼっていく。
キューバには、スペイン統治時代に根づいたカトリックと、アフリカから連れてこられた奴隷たちが持ち込んだ信仰が溶け合った「サンテリア」という独自の信仰がある。植民地支配や奴隷制の記憶、社会主義体制の影響を背負いながらも、人々は祈りを日常に根づかせてきた。
祈りはここで生きる人々にとって、歴史の痛みを乗り越え、日々を支えるための力でもあったのだろう。
その姿を見ながら、わたしは自分にとっての祈りを思い出していた。震災や戦争、残虐な事件で命が失われたとき、ニュースを前にただ無力感に押しつぶされながら祈ること。あるいは、正月に神社を訪れ、当たり前のように手を合わせる習慣。
幼い頃から続いてきた「日常の祈り」と、心がどうしようもなく揺さぶられたときの「切実な祈り」。その両方がわたしの中にはある。
人はなぜ祈るのだろう。祈ることで誰かを救えるわけではない。それでも祈るのは、自分にできる最小限の行為であり、自分自身の心をどうにか保つ方法だからかもしれない。あるいは、祈るという行為を通して、人と人とを目に見えない糸で結び直すためかもしれない。
わたしの祈りと、教会で出会った彼らの祈り。背景も形も違うけれど、「祈らずにはいられない」という根っこの部分はきっと同じなのだと思う。祈りは、国や文化の違いを超えて人をつなぐもの。
旅をすることが、人が大切にしてきた想いや営みに想いを馳せ、相手の心を考えることに繋がっていたらいいなと思う。
農村で感じる歴史と日常

ハバナを離れ、ヴィニャーレスの緑の谷へ。目の前に広がるのは、赤土の大地と石灰岩の奇岩が点在するヴィニャーレスの谷だった。空の青さと、どこまでも続くタバコ畑の緑。

畑を歩けば、牛が鋤を引き、ひとつひとつ葉を選びながら作業をする人々。そこで出会った青年は「父も祖父も、この土地で同じように働いてきた」と誇らしげに語り、タバコ畑や乾燥小屋を案内してくれた。
けれど、その裏には社会主義の仕組みや経済制裁の現実がある。タバコの多くは国に買い上げられ、現金を得るには観光客に少しでも葉巻を売るしかない。のどかな風景の奥には、制度や歴史が静かに横たわっていた。
それでも、家々の軒先からは夕食の匂いが漂い、洗濯物が風に揺れる。畑を耕し、家族と暮らしを営む。その当たり前の日常の力強さは、どんな政治や制度よりも鮮やかだった。
わたしは思った。歴史とは、教科書の中で語られる「遠い出来事」ではなく、この土地で生きる人々の日常そのものなのだと。社会主義の影も、経済の制約も、この赤土の上に積み重なった暮らしと共に存在している。
農村で過ごしたひとときは、歴史と日常が決して切り離せないことを教えてくれた。そして旅をすることで初めて、その当たり前の真実を自分の目と肌で確かめることができたのだ。
時間の重なりと未来への想い

2019年の夏に訪れたキューバ。あの旅を思い返すと、ふと考えることがある。あのときのわたしと、2025年のわたし。同じように時間は過ぎていくけれど、見える景色や感じ方は少しずつ変わっている。
キューバもまた、この6年間で変わったはずだ。アメリカとの国交回復、物資の充実、通貨制度の変更、観光客の増加。街の空気や人々の暮らしにも、ささやかな変化が積み重なっているだろう。
それでも、路地裏で出会った人々の営みや祈り、日常の小さな瞬間は変わらない。時間が経っても、そこに流れる「誰かの人生の奥行き」は、静かにそこに息づいている。
2025年の今、改めて思う。キューバの街角で出会った笑顔や祈り、農村の日常。そのひとつひとつが、観光地図には載らない「旅の宝物」だった。
変わる街と、変わらない営み。どちらもこの島の物語であり、わたしが胸に抱えて帰ることのできた記憶だ。
だからまたいつか、キューバに訪れたいと思う。あの青い海と人々の声に触れて、新しい物語を見つけるために。
All photos by Mao Haneda