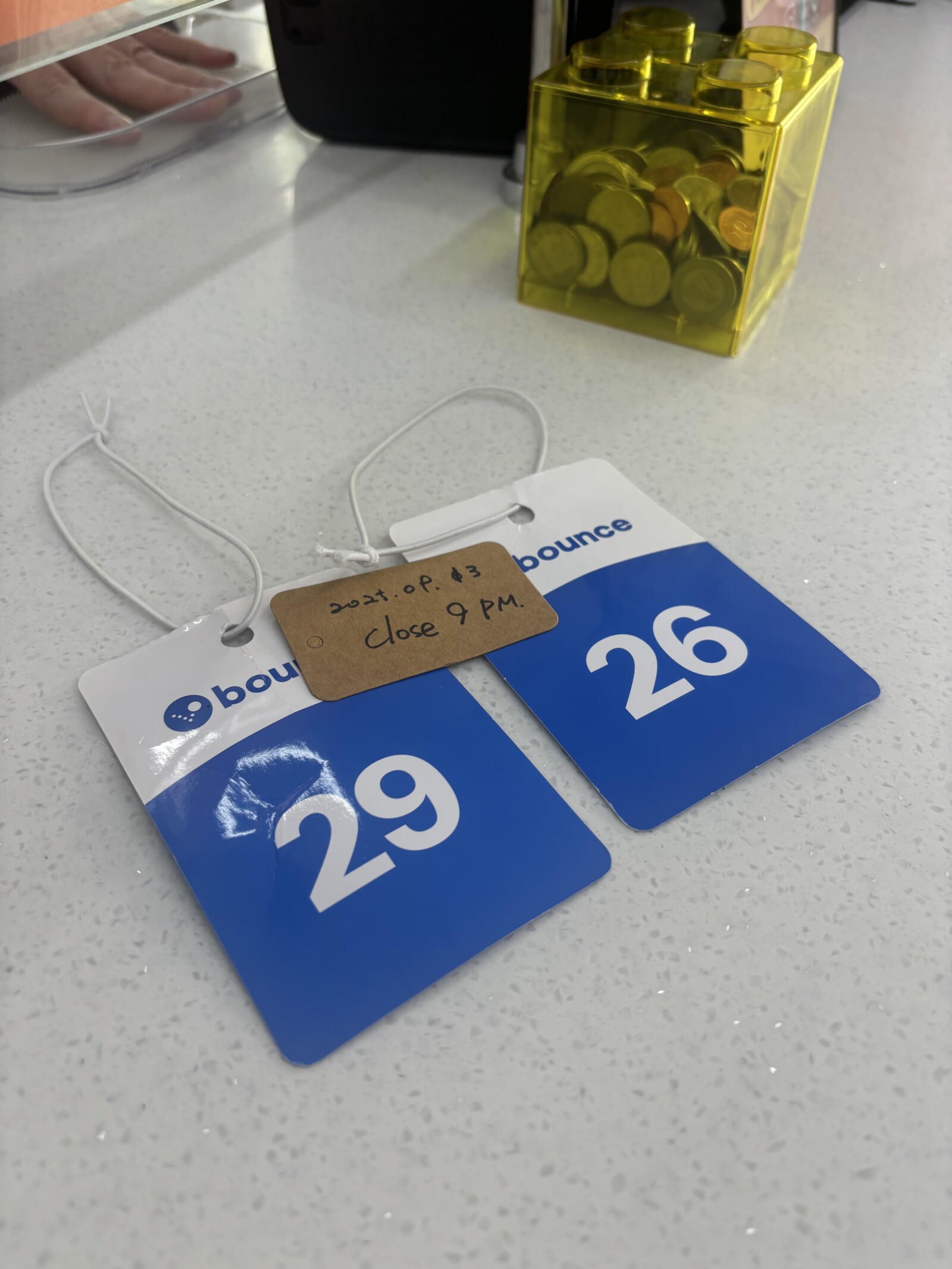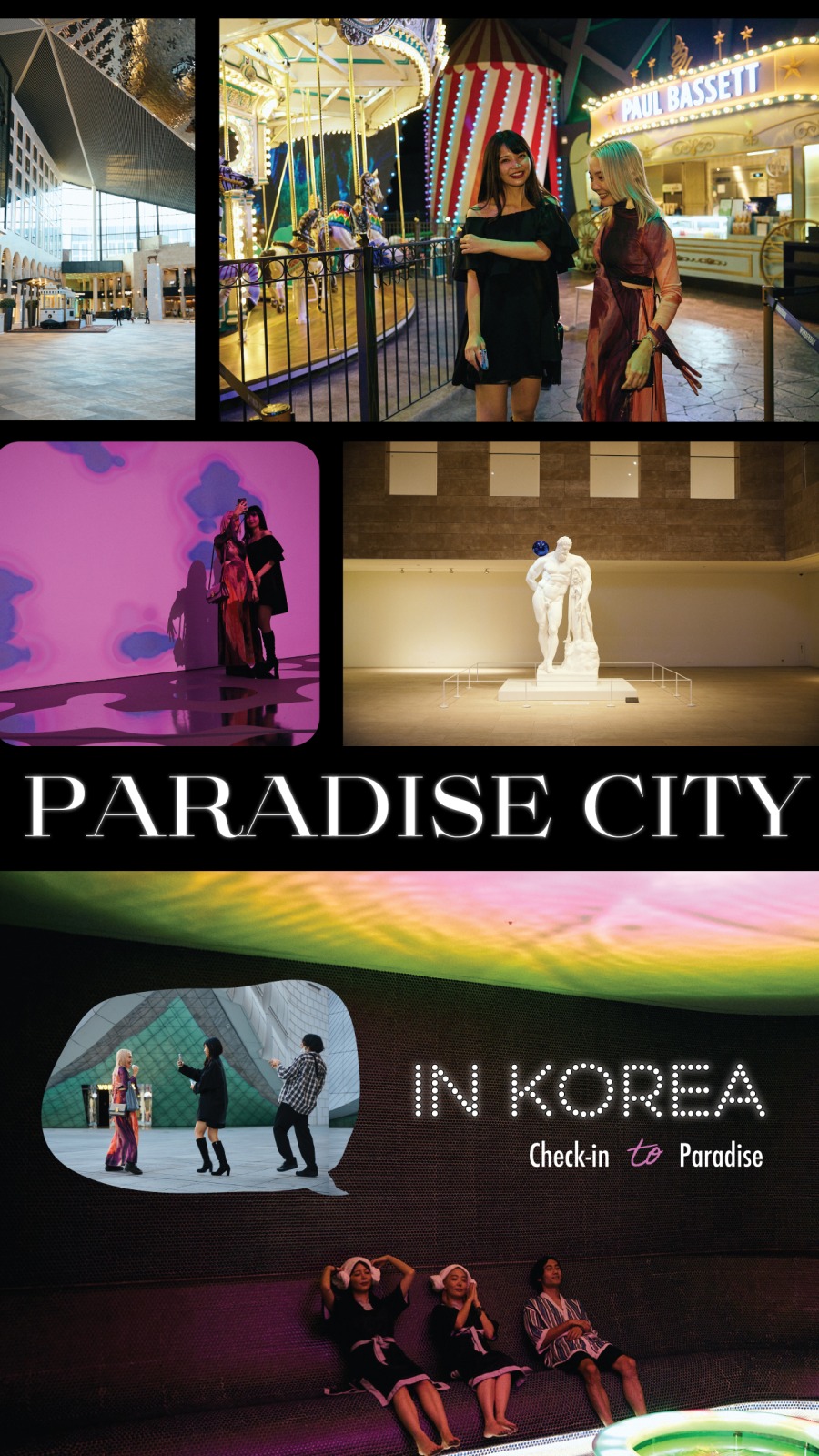旅中に感じたことはないだろうか。
盛り上がっている旅の気分をダウンさせる事件の1つは「ボラれる」という経験だ。バックパッカーである私たちはお金には非常にシビア。
他の旅人が1,000円で購入したポンチョに対して、自分は2,000円で買った事実を知ったときのあの敗北感。
「あとから振り返ればいい思い出」になるが、事件発覚時は沈み込んだ気持ちになる。
そんな失望感を味わわないために、旅人は「絶対にボラれまい!」という意思を強くして異国で買い物をするのだ。
ボラれないために必要なことは?
まずは以下2つが大事だと思う。
(2)交渉をする
私もバックパックを背負って世界を旅していたとき、これを徹底してやった。なので、ほとんどボラれることはなかった。

最安の価格で欲しいものを手にいれることができていた。ただ、その副作用として買い物がむちゃくちゃ嫌いになってしまったのだ…。
まず、「相場を知る」ためには、情報収集が必須だ。
訪問している国や町の物価はいかほどのものかをネットで調べたり、どの店で買うのがいちばんお得なのかを他の旅人に聞いてみたりと、結構な労力と時間を投資する必要がある。
これが面倒だ。もっと気軽にもっと思いのままに店に飛び込んで、一目惚れした商品を衝動買いとかしてみたくなる。

でも、「ボラれたくない」という強固な思いがそれを許さない。
そもそも、「どこの店が安いか」なんて情報は人生においてまるで役に立たない。そんなことに時間をかけるなら、その国の歴史とか政治とかを学んでるほうがよっぽど有意義だと頭ではわかっているが…。
「相場を知る」が終わると、次に店主と「交渉をする」必要がある。
値札なんてついてない商品は多いし、ついていたとしても、それは交渉のスタート価格という意味だ。にもかかわらず、海外経験がない旅行者は店主の言い値で買うことが多い。
定価に対する考え方
日本人ほど値札に忠実な国民はいない。なぜか。「定価」を発明した国は日本であり、日本は定価天国だから。
交渉の余地がない店がほとんどなので、値段交渉(駆け引き)の経験ないのだ。私が本格的に旅をしていたのはもう15年ほど前の話。当時の旅人たちはこんなことを言っていた。

本当は自分たちがボラれたくないだけなのだが…。私自身もそんな考えに侵され、日々、値段交渉に神経をすり減らしていた。わずか数十円のために大きなストレスを抱えながら。
その結果、買い物すること自体がメンドーでつまらないものになっていった。旅の後半になってそれに気がつき、いろんな疑問や考えが沸き起こった。
自分がその値段で買いたいと思ったんだから、別にそれでいいじゃないか!
相場研究に「時間」を無駄にしまくっているんじゃないか?
買い叩いて最安値で買うことが本当にいいことなのか?
アンフェアーなこの地球で、世界を旅できる幸運に恵まれた私たちが少しボラれたくらいでなんなのか。富の再分配だと思えばいいじゃないか。
確かに海外の市場やマーケットなど、日々の生活がかかっている人たちとの値段交渉は非常に価値ある経験だ。あのときに身につけた交渉力はいまの生活でも役に立っていると思う。
ただ、ボラれることを恐れて旅が楽しめなくなるのは本末転倒だとも思える。
当時、旅の後半戦からは「ボラれまい」から「ボラれたい」くらいの気持ちに切り替え、交渉力を鍛えるのではなく、店主とのコミュニケーションを楽しむ機会と捉え直すことで、旅の醍醐味である店巡りを謳歌できるようになった。
これからの考え方、「ギフトエコノミー」

ギフトエコノミーとは、「等価交換を主とする経済」ではなく、「見返りを求めず、与えることを優先する経済」のこと。
実践例として、有名なものにカルマキッチン(レストラン)がある。いろんなメニューが取り揃えてあるが、値段は一切書かれていない。
食後、テーブルには伝票の代わりに「封筒」が置かれ、その中のカードには以下のことが書かれている。
・この循環を続けたいと思えば、封筒に無記名で寄付を残すことができる
・封筒は閉店後に開封されるので、誰がいくら払ったか、もしくは払わなかったかは分からない
代金を支払う必要はないにも関わらず、支払わない人はほとんどいないそう。

交換ではなく「循環」、見返りではなく「贈り物(ギフト)」
そういう考え方をGiftivism(ギフティビズム)という。ポスト資本主義ともいわれる「ギフトエコノミー」。「足りないもの」ではなく「持っているもの」にフォーカスし、それぞれが与え合う社会。
ギフトエコノミーが広まっていくためには、「消費者」から「貢献者」へと意識を変える必要がある。これは旅の値段交渉の現場でも導入できる考え方かもしれない。
「ボラれた」ではなく「ギフトした」と。
目の前にいる人に自分が与えられるものは何か?そんなことを意識しつつ、旅する。
これからの旅人たちには、Giftivist(ギフティビスト)としての旅スタイルをぜひ楽しんで欲しいと思う。