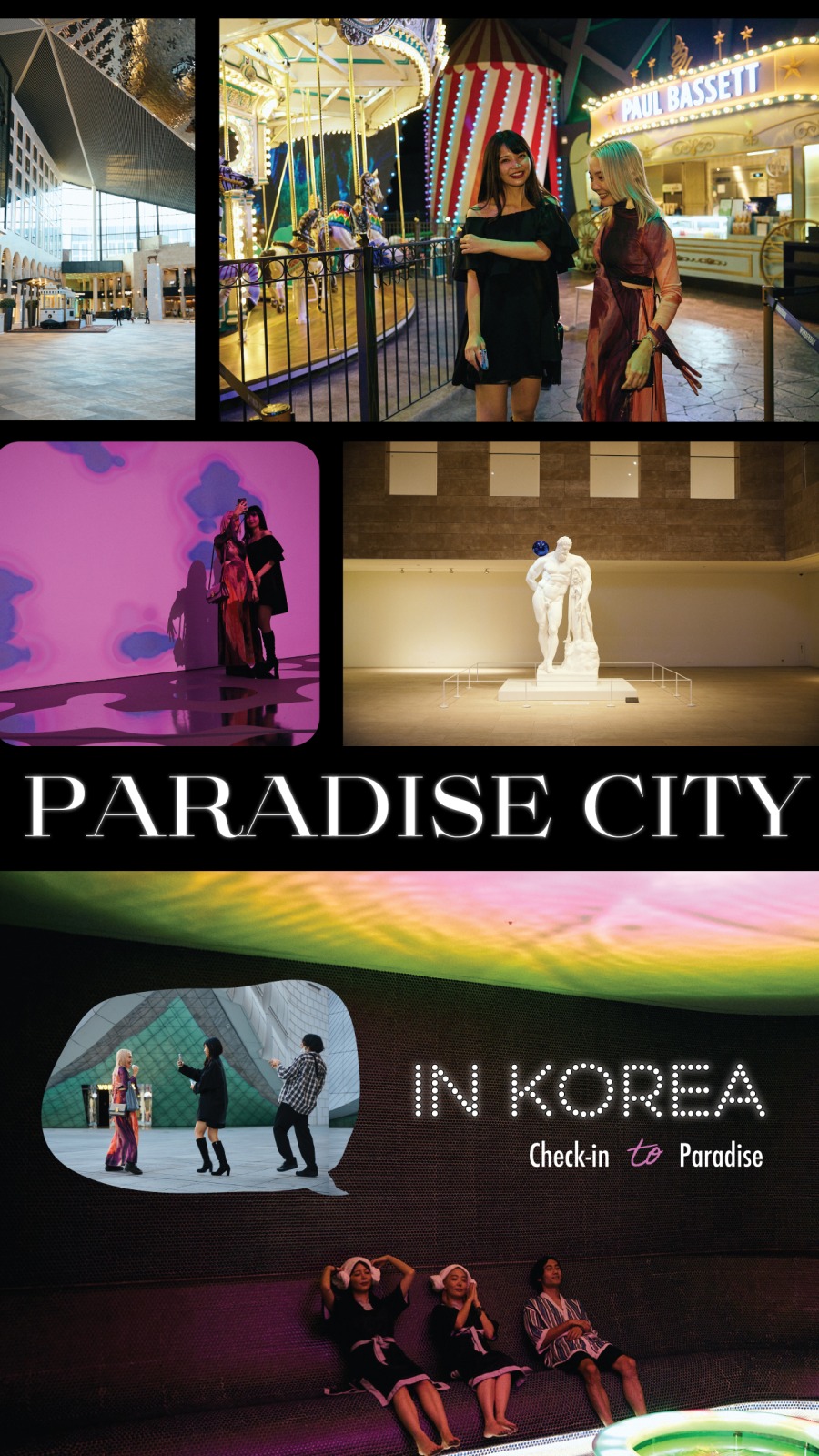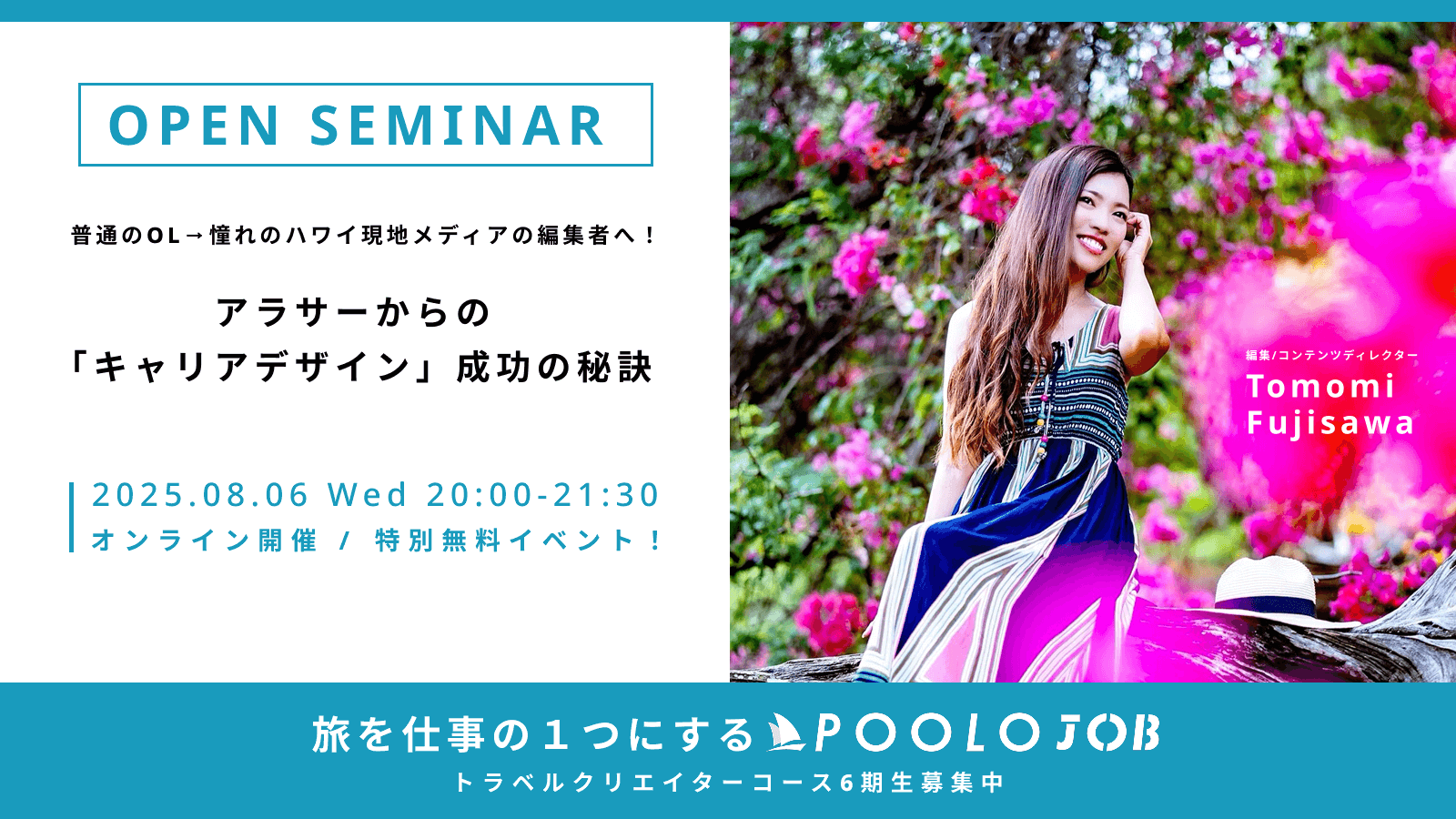「何がしたいかわからないなら、世界を見てこい。」
これは、中学2年生の進路検討の際、父に言われた言葉だ。これまで父に言われたなかでもっとも印象に残っている言葉でもある。
夜まで共働きの両親や、歳の離れた姉兄とすれ違いの日々に、小学生低学年だった私が寂しい思いをしないようにと、ある日両親がCS・BS放送を設置してくれた。海外ドラマやアニメが観れるようになり、その頃から日本とはまた違う、のびのびとしたライフスタイルや景色に興味をもち「海外生活」というざっくりしたものに憧れを抱くようになった。
家族や親戚の中にハワイ短期留学やイギリス留学、イタリアで修行をした人がいたり、中学2年間の担任が英語科の先生だったり、「海外」は私にとってわりと身近な存在だった。
彼らの話を聞く度に、外の世界への好奇心が膨らんでいった。
高校2年生になり進路について真剣に考える頃、せめて英語くらいは身に付けたいという気持ちはあったものの、特に学びたい専門分野や職種があったわけではなかった。
専門学校?大学外国文化学科?留学?ワーキングホリデー?
色々考えた末、私は比較的費用のかからないワーキングホリデー制度を使って憧れの「海外生活」をまず一年経験してみることにした。
滞在先は気候が良く自然豊かなオーストラリア。都市は、兄の友人が永住していて、私が一歳半の時に来たことのあった西オーストラリアのパースにした。
思い返せば、このたった一年の経験が今現在のわたしの生活の原点となり、この時得た教訓たちが今に活きている。
自然との共生が、素の自分へと戻してくれる
オーストラリアは平屋の家が多く、空が広く見えるのが特徴的だ。なかでもパースは街が一望できる公園や、ブラックスワン(黒い白鳥)がいる川、クオッカワラビーが生息するロットネスト島などユニークな自然に恵まれている。白い砂浜と真っ青な海のビーチは特に印象的だった。

Scarborough Beach
日本の地元の海ではバーベキューや雰囲気を楽しむ程度だったが、これほど美しい海を目の前にすると泳がずにはいられない。
ビーチに寝転がり、太陽の光を浴び、海水で絡まった髪の毛や全身砂まみれになることすらも、どこか心地よいものに感じられた。それはまるで、子供の頃泥遊びに夢中になっていた感覚を思い出させてくれた。
オーストラリアでの生活は、日常の一部を自然と共に過ごすことが多い。散歩、ピクニック、読書、サイクリング、友人とのおしゃべり。多くの時間を海や自然公園、ウォーターフロントで過ごした。
そんな自然のそばの時間は私の心を穏やかに、そして純粋な素の私へと戻してくれる感覚があった。
 Cottesloe Beachのサンセット。西海岸のパースではサンセットが見事に海に沈んでいくのが観られる。
Cottesloe Beachのサンセット。西海岸のパースではサンセットが見事に海に沈んでいくのが観られる。
日常のオンオフが、日々に充実感をもたらす
オーストラリアでは、日常のオンとオフが明確である。
一つ目に、日中は化粧をせず気楽な格好でいる人が多い点。サーファーが多いからか、道でもスーパーでも裸足で歩いている人をよく見かけるのはオーストラリアあるある。だがその姿も一変、夜になるとオシャレをして家族や友達との外出を楽しむ。わたし自身そんな生活を通して、格好に変化をつけるだけで、仕事や学業とプライベートの時間にメリハリがつきやすくなるのを感じた。

Scarborough Beachでバーベキューパーティー
二つ目に、オーストラリアではカフェやスーパー、ショッピングセンターは夕方には閉まり、24時間営業なんて店はない。バーには仕事着のまま飲み始める人々が15時頃から増え出す。
また、屋外の至る所に公共のバーベキューグリルが設置されているため、昼夜問わず友達や家族とのひと時を楽しむ人々で賑わうのもオーストラリアらしい光景であった。
「必要な分だけ働き、それ以外は自分の趣味や大事な人との時間に充てる。」
残業や24時間営業のお店が当たり前のようにある日本で育った私にとっては、とても新鮮な価値観だった。
これはより幸せを身近に感じるための秘訣だ。
いつだって自分らしく在っていい
街の雰囲気に合ったおしゃれなカフェに入った時に、店員のお姉さんの自由なフッションに驚いたことがあった。
ピアスや指輪は何個も重なり、爪は綺麗に色が塗られ、腕いっぱいに今時のファッションタトゥー、ショートパンツとキャミソールにドクターマーチン風のブーツ、そしてお店で支給されているであろうエプロン。決して派手な感じでもなく、むしろ店内のおしゃれな雰囲気にマッチしているのだ。
細かい身だしなみや服装の規定があるなかで働いてきた私にとって、純粋に、自分の好みや個性を大切にしながら仕事ができる環境が魅力的だと感じた。
またビーチでは、若者たちに並び、おばあちゃんたちも色や柄物のビキニ姿で日焼けを楽しんでいる。その背中には、若い頃から太陽を存分に楽しんできた証であろうシミの数々。そしておじいちゃんたちは美味しいビールをたらふく飲んできたであろう立派なお腹を堂々と出し、気持ちよさそうにしている。
 巡回中の警察官に自作ラップを聞かせるタイ人の友達。
巡回中の警察官に自作ラップを聞かせるタイ人の友達。
相手によらずマイスタイルな友達と、こんなおちゃらけにも付き合える警官の柔軟さに拍手。
生まれ持った個性、年齢や体型など、周りの目を気にせずに、好きなものを身に纏い、好きに表現し、自分らしくいることを楽しむ人の姿はいつでも素敵だと思う。
シンプルさがもたらす心の平穏
 仕事中にかかったダブルレインボー。障害となるものがなく端から端までの完全な虹を人生で初めて見た日。
仕事中にかかったダブルレインボー。障害となるものがなく端から端までの完全な虹を人生で初めて見た日。
基本的にワーキングホリデービザが適用するのは1年だが、特定業務に3ヶ月以上従事することで、もう一年延長できるセカンドビザ取得がある。そのセカンドビザをとることに決めた私は、西海岸パースとは真反対の東海岸にあるカブールチャーという田舎町で、住み込みのいちごファームでの仕事を見つけた。
周辺には繁華街や娯楽施設はほとんど無く、同じ場所で働くハウスメイトたちと毎朝同じ時間に起き、日の出を見ながら同じ時間に出勤し、同じ時間に寝て、同じ日に休むという生活を3ヶ月間送った。
変に欲を刺激するようなものがないため、ただ彼らとのご飯やゲームの時間を楽しみ、外出用の洋服やコスメを買い足す代わりに、土台となる身体作りなんかに励むようになった。
必要以上にものや選択肢を持たないシンプルな生活を送ることで何が本当に大切なものかが見え始める。必要なものだけに集中することで余計な思考や悩み、欲に惑わされなくなり、平穏な心を体験できることをここで知った。
 ハウスメイトの台湾人カップルが作ってくれたタロ芋のタピオカドリンク
ハウスメイトの台湾人カップルが作ってくれたタロ芋のタピオカドリンク
住めば都
高校を卒業して一年間、少しでもワーホリ生活の足しになるようにと毎日アルバイトに励んだ。幸いなことに仲間に恵まれ、渡豪直前には沢山の暖かい応援をもらった。
その反動もあってか、いざオーストラリアへ渡ると、すぐにホームシックと言葉の壁にぶつかり、不安と寂しさで涙を流す日が続いた。
1ヶ月間だけのホームステイでは、当時14歳で私と同じ語学学校に通う中国人の女の子と短期間だけ一緒に住んだ。初日は一緒に通学したが普段は時間帯が違うため、エレメンタリー(小学生)レベルの英語力しかなかった私のために、学校までのバスの乗り方や行き方を丁寧に紙に書いて渡してくれた。それ以降も、まだ来たばかりで右も左もわからない私の面倒を見てくれて、当時19歳の私とどちらが年上かわからないくらい彼女に頼る日々だった。
そんな私も10ヶ月も経てば生活に慣れ、レストランで仕事にも就き、なんだかんだ帰国したくないとさえ思えていたのだ。成人式のために一度帰国したものの、その2年後には再びセカンドビザで戻ってくる選択さえとった。
 パースシティの街並みが見えるウォーターフロントでの一枚
パースシティの街並みが見えるウォーターフロントでの一枚
「住めば都」と言うように、時間と共にその環境に適応し、居心地の良ささえ見出せるようになる。
苦いことも楽しいことも経験し、時間をかけて魅力を見つけていったその場所は、何年経っても「帰る場所」として私の心に存在する大切な「都」となるのだ。
世界中の人と出会うことで、世界が広がる
オーストラリアで出会った友達は数知れない。パーティー文化が盛んなため、毎回のように新しい人々との出会いがあった。
 語学学校で仲良くなった友人たちとタイで再会した時
語学学校で仲良くなった友人たちとタイで再会した時
全ての友人と頻繁に連絡を取り合うわけではないが、旅行の際にはその土地に住む友人に連絡を取ることが常だ。

コロンビア・カルタヘナを訪れた時。コロンビア人の友達が多く、実際に彼らのホームタウンが見れたのは嬉しかった。
友人たちの住む場所が、新たな「目的地」として私の旅の目的を形取っている。再会を通じて仲が深まったり、現地の生きた情報を得ることができる。彼らの故郷を訪れることで、その土地の魅力をより知れるし、彼らのルーツを知ることで、彼らとの繋がりや理解がさらに深まる。
旅を通して人に出会い、その人を通して訪れたい次の目的地がまたできる。
友達が世界中にできたことは、まさに「世界が広がった」という言葉そのものだった。
挑戦したからこそ今がある

オーストラリアという新しい環境での一年は、私にとって単なる「海外生活」ではなく、視野を大きく広げた貴重な旅となった。
冒頭で述べた「何がしたいか」の答えが見つかったわけではなかった。
けれど何もかもが未知で、不安と期待が入り混じる中で踏み出した一歩が、「今のわたし」をかたち作った。オーストラリアで出会った人々、景色、文化、そして自分自身との対話が、私の中に新たな価値観を根付かせた。
未知の土地へ向かえば、新しい世界が広がり、新しい価値観に触れることで自分の器が広がり、より良い自分へと成長させる。
きっと「新しい土地へ旅にでたい」という欲求は、また一歩ステップアップしたいという衝動にかられている時なのかもしれない。
All photos by saeno okuyama