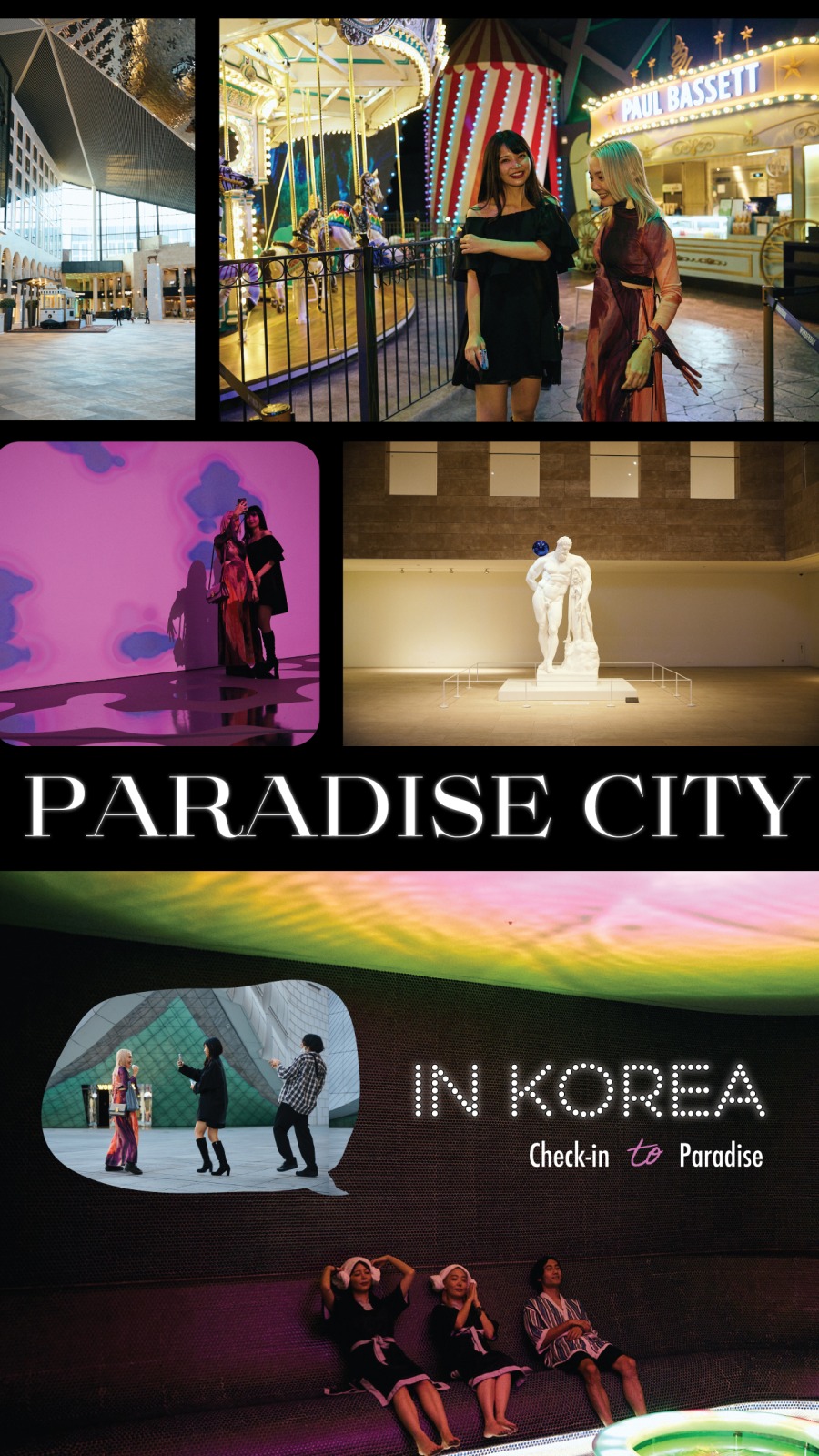旅のきっかけは東京で見つけた一冊の本だった。
『雪』(オルハン・パムク著)を読み、その舞台地となったカルス行くのがずっと夢だった。
じつは旅人には読書家も多い。SNSで流れてくる綺麗な写真や旅の様子を見て旅に想いを寄せるのも良いけれど、ひとつの選択肢として書店から始まる旅というのも僕はお勧めしたい。
そこには著者が作り出した物語と読者の想像力が合わさって、いつもとは一味違う旅が待っている。僕は著者の書いた物語を何度も読み返しながら、今回のトルコの旅へと向かった。
トルコ最東の小さな町・カルス

トルコの首都アンカラから鉄道でカルスに行くことが僕の長年の夢だった。
東京の書店で初めてトルコの文学作品『雪』を見つけてからカルスという町に想像を膨らませていたからだ。
『雪』は、都会から来た詩人と、雪に閉ざされた小さな町の人々とのすれ違いを通して、トルコの矛盾や葛藤を描いた作品だ。その舞台となったのが、僕がずっと憧れていた町・カルス。小説を読んでいるうちに、この雪深い町を自分の目で見てみたいと思うようになっていた。
アンカラから鉄道で12時間ほどの旅路、ちょうど雨が降っていたということもあり列車から見える景色は何だか寂しげだった。あの作品もそういえば終始暗い雰囲気を醸し出していたなと雨粒のついたガラス越しに灰色の風景を眺めていた。
列車内も皆沈黙していてとても静かだ。誰もがこの寂しげな雰囲気を感じて自分の心の中で自分と会話しているのかもしれない。旅をしていると自分との向き合いも大切になってくる。
1人でバックパックを背負い歩く旅はその全てを独り占めできる貴重な時間だ。日が完全に落ちた時間帯に列車はカルスに到着した。
長年待ちわびていた、この瞬間がついに来た。足早に列車を降りる。
観光客があまり訪れない場所だと思っていたのだが、意外にも同じ列車には西洋からのバックパッカーが多く乗車していたようだ。
僕は初めての町でトラブルに遭わないように、急いでネットで見つけていた宿へと向かう。探していた宿はすぐに見つかった。町の中心地で大きなモスクのすぐ横に位置していた。
田舎にもこんなに大きなモスクがあるのかと宿の入り口からモスクを眺めた。だんだんとこの地域の信仰心の高さが伝わってくる気がした。
先に受付している人々が部屋へ向かったので受付に向かう。予約はしていなかったので少し緊張しながら尋ねてみた。
「Merhaba! rezervasyon yok ama bir boş oda var mı?」
予約していないのだけど、空いている部屋はありますか?
そう尋ねると「もちろん」と言われ難なく宿を確保することができた。受付を宿のスタッフさんがしている間も座って休んでいてくれと、チャイを入れてくれた。
雨で冷えた体が、湯気の出るほどのチャイで温められていく。何だかすごく幸せだった。
チャイをご馳走してもらった日

早朝からアザーン(イスラム教の礼拝の呼びかけ)の放送で目を覚ました。地元の人たちが通りの向こう側のモスクへと歩いていくのが見える。
シャワーを浴びて、身なりを整え、カメラを斜めがけして姿鏡で今日はきっと良い日になると心の中で思う。
まだ知らないことに出会うかもしれない。初めての土地に来たらいつも感じる静かな胸の高鳴り。
僕の旅はまず町を知ることから始まる。朝食は食べずにひたすら歩いて町を見る。カルスの町は主要な観光名所が多いというわけでもないので、案外簡単に全容を知ることができる。
路地を歩いているとガチョウがゲージに入れられているのをよく見かけた。
その周りに人々が集まり何かを話している。すると、タクシーがやってきてタクシーのトランクにガチョウが次々と詰め込まれていく。
なんともワイルドな光景だ。驚きと共に僕の見てきたトルコとの文化の違いを感じた。
その光景を少し遠くから珍しそうに見ていたからだろうか。後ろから男性2人に声をかけられた。
「何を見ているの?」
「あの光景が珍しくて。」
「君は写真も撮るのか?」
「そうだよ、僕は写真家なんだ。」
僕らの写真も撮ってくれと壁の前で撮られる準備をする2人。
トルコではこんなことがよくある。そこで写真をくれという人もいるけど、ただ撮られるだけの人もいる。彼らはなにも要求しないタイプだ。シャッターがなり終わると彼らはチャイは好きかと尋ねてきた。
「チャイ⁈大好き!」
「なら、チャイを一緒に飲まないか?」
トルコ人はよくこうやってチャイを一緒に飲もうと誘ってくる。チャイはトルコ人にとって「君と話したい」という合図なのだと思う。
彼らに連れられ、しばらく歩いた。ついた場所はバス会社の事務所だった。彼らは都市間移動のバス運転手だった。
長距離を運転するバス運転手は目的地に到着すると仲間たちとチャイを飲みながら休憩する。そんな光景を田舎ではよく見かけた。でも、まさか自分がそこに混ざる日が来るとは思わなかった。
チャイで生まれる人の繋がり

バス会社の事務所内には8人くらいの男たちが薄暗い中でチャイを飲みながらおしゃべりをしていた。
急に外国人の僕が入ってきたので少し驚いた顔を見せたが、事情を聞くとすぐに歓迎してくれた。自分たちの席をあけてここに座れと歓迎してくれた。
まだ冬が明けたばかりの季節ということもあり、部屋にはとても古いストーブが置かれており、男たちの中の若い1人が僕の前にストーブを移動して持ってきてくれた。トルコ人のこういうおもてなしの仕方は本当に感激するほど心を打たれる。
僕の前に湯気が上がる熱々のチャイがカタンッという音と共に置かれた。僕がチャイに一口つけて一息つくと、彼らの質問攻めが始まった。
「君はどこからきたんだ?」
「なんでこんなところまで?」
「カルスはどうだ?僕らをどう思う?」
彼らはイスタンブールや他の大都市に比べて信仰をとても大切にする人が多い。それを彼ら自身、外からどう思われているのか気になるのかもしれない。
僕は終始笑顔でカルスにずっと来たかったのだと伝えた。トルコ人作家の本にこの場所が出ていたので、とても興味があったのだと。
彼らは嬉しそうに、カルスの観光名所を教えてくれた。町を見渡したいと言うと、カルス城が近くにあるからそこに行ってみると良いと言われた。
トルコを旅していてチャイを一緒に飲もうと言われることがよくある。彼らにとってチャイは休息で、仲間たちとの大切な時間を楽しむ道具であり、おもてなしなんだと思う。
僕はいつもその優しさやおもてなしに甘えている。日本にいると人との関わりが薄くなって少し心が寂しくなってしまう。
だから、トルコでチャイを飲もうと誘われるたびに誰かと時間を過ごすことがこんなにも幸せなんだと再確認させられてしまう。
『雪』の主人公は都会的であることを誇りに思っていた。
先進的な考え方、生き方を良いものだと、田舎の人は信仰を重視するあまり遅れていると心のどこかで感じていたように見えた。でも、僕は今の日本が都会的、先進的な人間の生き方をしているというなら、人間は無機質なものになっていくのではないかと思う。
だからこそ、都会とは縁のないような場所で人々に出会うと自分の生き方について考えさせられてしまう。僕が旅をしているのは人に出会いたいという無意識の欲求があるからなのだと感じた。
カルスの町が僕に教えてくれたこと

カルスではいろんな人に声をかけられた。アジア人がこんなに遠くまで来ていることが珍しかったのだと思う。
カルス城の頂上から眺めた景色はとても美しかった。イスタンブールとは違った自然と人が共存しているような景色。周りを山に囲まれ、その一角に人々が生活している。
休みの日になれば友人と公園でおしゃべりをしたり、仕事の合間にチャイを片手に笑い合う、仕事をしている人々でさえどこかのんびりしている。
町を一望できるこの場所からそんな町の人々の表情を思い出していた。『雪』ではこの町ではいろんな策略と事件が繰り広げられていた。でも、僕の体験した物語はそれとは全く逆の温かい物語だった。
カルスからイスタンブールへ向かう最後の日。夕方、近くにあった小さなモスクを訪れた。
緑色のカーペットが広がっていた、窓から夕差しが入り込んでいる。凝った装飾は施されていなかったが、人一人いないこの空間はなんとも神秘的だった。
僕はしばらく、一人で体育座りをしていた。祈りを捧げるとか、考え事をしていたとかそんなわけではなかった。
ただ肩の力を抜いて座っていたかった。本当ただは眠かった。
空にオレンジ色の波がたった頃、イスタンブール行きの列車が少しずつ動き出した。車窓から見えている景色は来たときと同じはずなのに、何だか違うもののように感じた。
トルコの文学作品から始まった物語は僕の物語に移り変わろうとしていた。見たもの、感じたもの、この町でもらったたくさんの優しさを忘れないように持ち帰ろう。
この記事を書くことで、もしかしたら誰かがこの小さな町に興味が湧くかもしれない。そしてまた、新しい物語ができていく。
カルス。本当に良い旅になったなー。ありがとう。






All photos by Kakeru Yamashiro