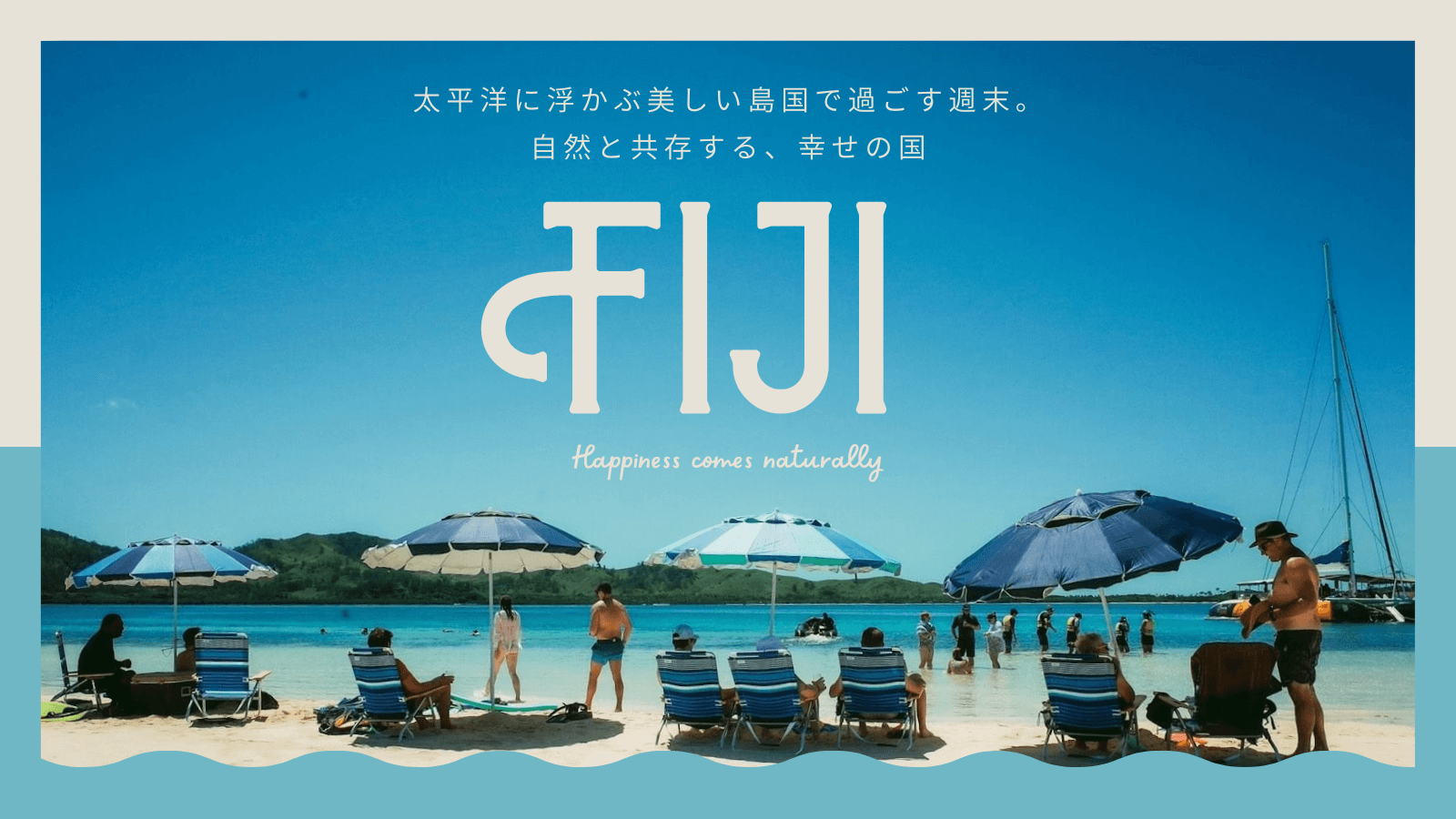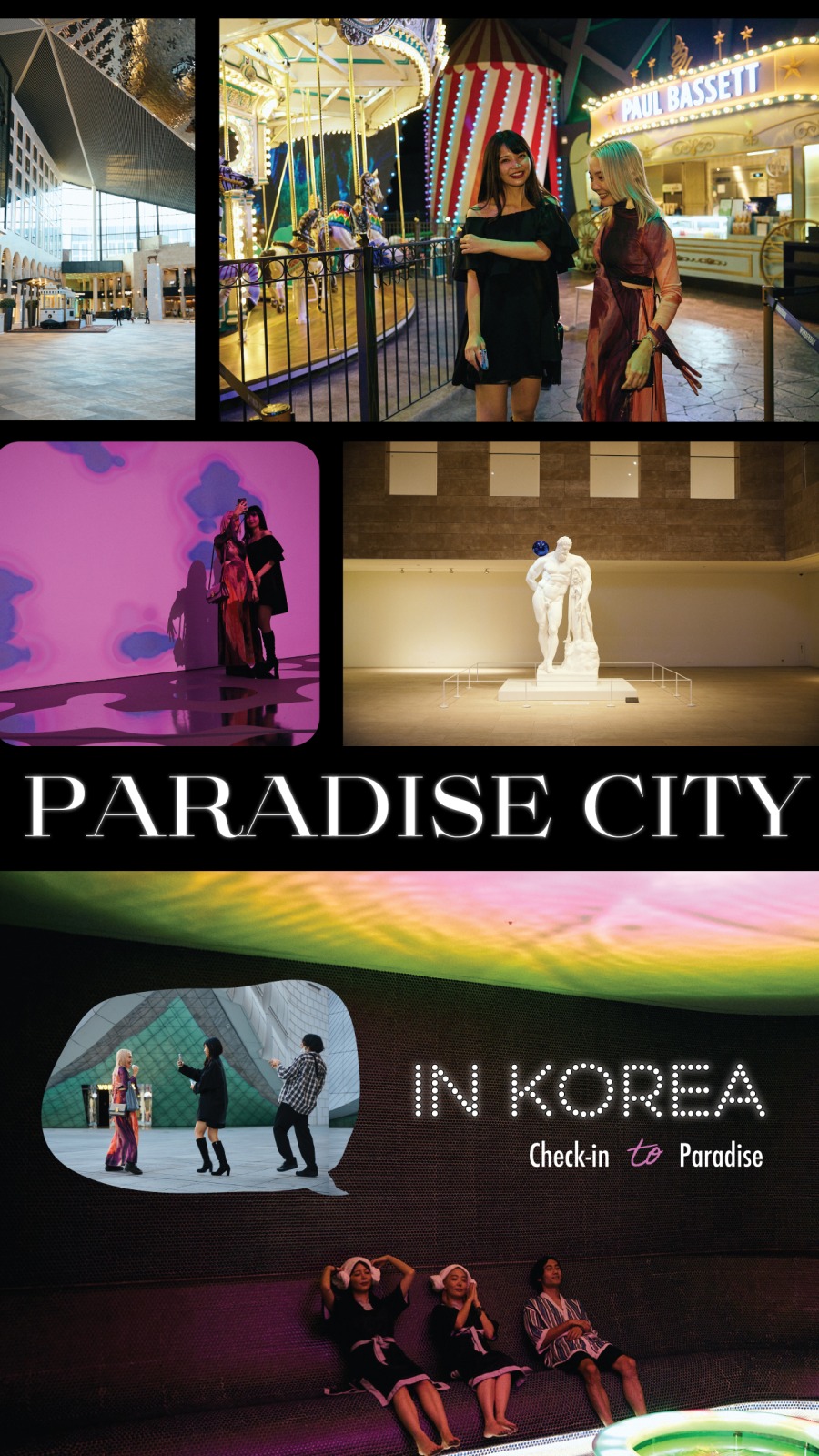これまでの旅は娯楽や消費が目的の中心にありました。しかし、旅を通じて得られるものはそれだけではありません。たとえば、生き方や暮らし方のヒントになるような学びを得られたり、訪れた地域に住む方と交流を育んだり。
こうした刹那的ではない旅の在り方を、TABIPPOでは「あたらしい旅」と称し、旅のスタンダードにしようとしています。とはいえ、その道のりはまだ遠く、さまざまな角度から方法を模索している最中です。
今回は、日本の「今」を写真とともに未来へと語りつなぐ『日本再発見プロジェクト』の第1弾で語り部を担った写真家・立木義浩さんと、ライター・モデル・SNSプランナーとして活動するたけもこさんをゲストに迎え、旅と創作にまつわる話を伺います。
ファシリテーターを務めるのは、TABIPPO代表取締役の清水直哉。“今と昔”の旅を振り返りながら、旅はどう変わったのか、また変わらずあるもの何か、そして旅は創作にどのような影響を与えるのかについてお聞きします。


時代を経て、旅はさらに自由で多様に
清水:今、日本では若者の旅行離れが進んでいると言われています。これは僕自身もなんとなく実感できるところでもあって。今って無料で楽しめる娯楽がいくらでもあるんですよ。
それと比べたら、旅行はお金も時間もかかる、つまりコストパフォーマンスもタイムパフォーマンスも悪いということになります。でも、旅の魅力って費用対効果だけで測れない側面もたくさんあると思うんですね。
僕は最近、訪れた場所にできるかぎり深く入っていきたい気持ちが強くて。だから、スマホで検索してすぐに出てくるような場所は避けて、観光客が普通だったら運ばない場所に行くようにしています。
たとえば、地元の人が足繁く通うお店とか、その土地の歴史を深く知れるような場所とか。そのほうが自分の生き方とか働き方とか、もっと言うと死生観とかに影響を与えてくれるんですよね。ちなみに、たけもこさんは旅についてどのように考えていますか?

たけもこ:20代前半くらいまでは写真映えを意識して場所を選んでいたのですが、最近は誰と一緒に時間を過ごすのかを大切にするようになりました。先日も友人と山形に行ったのですが、いつもと違う場所での会話って普段とは少し違う気がしていて。絆をさらに深めるきっかけになったと思います。
清水:立木さんはいかがですか?
立木:そもそも俺が若い頃は、 旅行という概念がそこまで浸透していなかったからさ。それよりも生きていくことで精一杯。そんななかで吉行淳之介や開高健といった作家の書く文章を通じて、旅とはどういうものかを教わった気がするね。
吉行淳之介の「街角の煙草屋までの旅」というエッセイでは、坂の上の角の煙草屋まで行くのも旅なんだって書いてあるわけよ。遠くに行かなくても、こちらの感性次第で日常が旅になるっていうことなんだけどさ。そういう気づきに対して、新鮮な驚きがあったね。

清水:確かに。海外渡航が自由化されたのが1964年だから、現在のような旅行のスタイルが確立されたのって割と最近の出来事なんですよね。
立木:しかも、当時は固定相場制で1ドルが360円だったから、自分の金で海外に行くなんてとても考えられなかった。それもあって、仕事で海外に行く機会があると空いている時間を利用してひたすら自分の写真を撮っていたの。
とはいっても、宿泊先の周辺を散歩するぐらいしかできないから、 スナップの世界に入っていくわけ。それで人を撮るためのコミュニケーション術や、危険を察知する嗅覚を身につけていったんだよね。
清水:旅先でもっと写真を撮りたいと考えたことはなかったんですか?
立木:考えていたとしても頻繁には行けなかったからさ、一度の滞在で全部すくい取ってくるくらいの気持ちでいたね。でも、撮った写真のすべてが形になるわけじゃなくて、ピカっと光る何かを持った写真を選び抜くことも大切なの。
だから、日本に帰ってきてすぐにコンタクトシートをつくるんだけど、1カ月後とか半年後に見直してみる。そうすると、ほとんどはボツなんだけど、なんでこれを選んでいなかったんだろうっていう1枚が見つかることがあるわけ。

たけもこ:私も文章を書いているとき、見直すことの価値を感じる瞬間があるのでわかります。自分のメモを見返すのってすごく恥ずかしいんですけど、「このときはこう考えていたんだな。でも、今ならこういうふうに理解し直せるな」って思うことがあって。
立木:ある時点で自分の能力に自信を持って誇らしく思う矜持(きょうじ)が身に付くんだけど、それを捨てきれずにいると、勘違いの人生になるから、矜持を捨てるためにも含羞(がんしゅう = はにかみ、はじらい)は持ち合わせてるのが良いんだね。活動が軌道に乗って、人に褒められるようになると足元が浮いてるような感覚に陥る時期があってさ。
そういうときがいちばん危ない。でも、俺の場合は写真が救ってくれることがあるの。もちろん、写真は喋らないよ。でも、ものは言う。それを自分で感じ取って、手本にできるかが重要なんだよね。
時間をかけて育まれる関係や価値
清水:今回の「日本再発見」プロジェクトでは沖縄の八重山諸島を訪れていますが、どのようなことを考えながら写真を撮っていましたか?
立木:琉球王国や第二次世界大戦といった歴史が積み重なっている場所ということもあり、先祖をすごく大切にしているし、血縁、地縁も強い。そういう場所に他所からふらっと来た人間が「写真を撮らせてほしい」と急にお願いしても警戒されるだけでしょ?
何度も足を運んで島民と関係を築くところからはじめたんだよね。あと、沖縄には海の彼方(ニライ・カナイ)志向があって、それは先祖との交流の世界だそうだ。夕凪の静けさの中に居ると全身で感じることができる。それを写真に収められたら最高。

立木:これは余談なんだけど、与那国で転んで鼻を折っちゃったのよ。でも、診療所しかなくてさ。その場所を教えてくれたおばちゃんがすごく元気な方で、お医者さんが来るまでの間に「あなたいくつなの?」「私は75歳。あなたは?」「俺は85歳」「負けた!」みたいな会話で盛り上がって、後日御礼に粗品を送ったら、返信として大きな魚が送られてきたから驚いたけど、嬉しかった。
いろいろ調べたらけっこういい値段なの。これはもう一度何か送らないとダメだと思ったんだけど、それなら直に挨拶に行こうかなと考えている最中なんだよね。
清水:素敵な出会いがあったんですね。旅先で訪れた人と交流を育んでいくのは、僕たちが考える「あたらしい旅」の理想にも近いので、すごく参考になります。
立木:一方で、仕事でお世話になったのに、それから一度も足を運んでいない場所なんて山ほどあるわけだから、俺は死ぬときに「失礼しました」と思うような気がするんだよね。棺桶のなかで寝ていたら、お辞儀ができるかわかんないんだけどさ(笑)。
ただ、写真をプリントしてプレゼントするってことは割としてきているから、日本中に俺の撮った写真が散らばっていると思う。
清水:プリントされた写真ってパソコンの画面上で見るものとは質感が違いますよね。目との距離感によっても印象がだいぶ変わるというか。
立木:そうそう。プリントされた写真を遠目から俯瞰で見たり、近寄って細部を見たりっていうこと自体が減っているでしょ? 今はスマホで簡単に写真が撮れる時代だし。文章にもそういうことある?
たけもこ:パソコンで書くのと、紙に手書きするのはやっぱり違いますよね。
立木:鉛筆がいいか、ボールペンがいいかみたいな選択もあるしね。
清水:今思い出した話があるのでしてもいいですか?
立木:どうぞどうぞ。

清水:僕、清水直哉っていうんですけど、白樺派で有名な志賀直哉が由来で。しかも何の因果か、最近になって志賀直哉と縁がある場所を訪れる機会が増えているんです。たとえば、香川県の琴平町で仕事をしているのですが、そこの宿に志賀直哉が何年か滞在して文章を書いていたことがあるらしくて。
山道とかに痕跡が残されているんですね。そうやって時代を超えて価値ある文章が残されている一方で、僕たちがスマホやパソコンで書いている文章ってどこにも残らない可能性があるんだなっていう感覚があるんです。もちろん、それが悪いわけではないんですけれど。
たけもこ:私、頭のなかで考えていることはすべて文字化されたらいいのにって思うくらい、文章にすることに価値を感じているのですが、一方でそれを必ず発信しなくちゃいけないとは考えていないんですね。
自分の中にあるものを外に出すことで客観的に見ることができるから、「こんなことを考えていたんだ」と驚く瞬間があるのが面白くて。自分が知らない自分を認識できるのは、文章を書くことの楽しさのひとつなのかなと思います。

立木:今の時代はさ、いろんなことが消費に向かっていくわけだよね。だから、ちょっと有名になったからといって10年後にどうなっているかと言われたらほとんどの人が覚えていないと思う。そうやって消費されていくことに対して、どこかで意識的にならないといけないよね。場合によっては、自分の楽しさのために創作をしてもいいわけだし。
たけもこ:それもあって、最近はクローズドな場で文章を書く機会を増やしているんですね。実はものすごくビビりだから、私の文章を読みたい人だけ読んでくれればいいやって最近は考えるようにしています。そのなかで、評判がよかったものは公開してもいいかなくらいの温度感のほうが気も楽なんです。
旅を通じて創作はさらに面白くなる
清水:立木さんが参加された『日本再発見プロジェクト』も、後世に写真文化を繋いでいくという点で消費とは違う方向に向かうんだという意志を感じます。
僕とたけもこさんは大阪で開催された立木さんの写真展にも足を運んでいるのですが、なかでも目を引いたのが海沿いで女の子がリフティングをしている写真でした。ちょうど顔のところにボールがきていて、シャッターを切るタイミングがすごいなって。

立木:もちろん、それ以外の写真もあるんだよ。でも、顔がボールみたいになっているのが面白くてさ。俺以外にも笑ってくれる人がいるんじゃないなと思って展示会場でも遠巻きに眺めていたんだけど、あの日はいなかったね(笑)。
清水:奇跡的なシーンを捉えるすごさを感じました。あと、海の近くでボールを蹴っているけれど、落ちたりしないのかなって。
立木:そうやって1枚の写真に対していろいろ感想を言ってくれるのはすごく嬉しい。そうするとね、調子に乗ってまたいい写真が撮れるから(笑)。

清水:たけもこさんが気になった写真は?
たけもこ:私は動物の写真に惹かれました。
立木:これは牛を撮ろうと思ったの。それでストロボを点けて構えようとしたら、イノシシが出てきたもんだから慌てちゃって。本来であれば、被写体が真ん中にくるのがセオリーなんだけど、そのときは咄嗟のことだったから随分と端っこのほうに写っているんだよね。ただ、そうやって自分の意図から外れたタイミングで撮れる写真も面白さのひとつだから。

たけもこ:写真のフレーミングってある種の制約じゃないですか。文章にも文字数という制約があって、何を書いたのかと同時に何を削ったのかが大事だと思っているので、通じるものがある気がします。
立木:そうそう。制約があるから面白いんだよね。写真の場合、1:1とか19:6とかってフレーミングを選択できるのが楽しみのひとつになっていると思う。
たとえば66っていうカメラは、真四角に撮れるから画角に困ったときにフレーミングが助けてくれるのよ。縦横のサイズが同じだから、被写体を真ん中に置くか、 左に置くか、右に置くか、あるいは少し下げるかっていう選択だけで済むの。
俺より上の世代にリチャード・アヴェドンという有名なフォトグラファーがいて、66のカメラをよく使っていたんだけど、そのままのフォーマットで雑誌に掲載されているから、真四角の写真がバーンって力強く目に入ってくるの。そのときの衝撃は今でも心に焼きついているね。
清水 :こうやって立木さんから話を聞いて、人柄を理解したうえであらためて写真を見てみると、また違った印象がします。
たけもこ:立木さんの写真を見て、難しくないなって真っ先に思ったんですね。すうっと入ってくるというか、私でも見ていいんだっていう気になるというか。良い意味で大御所感がない。そう感じた理由が、立木さんと実際に話してみてわかりました。こんなにピュアな人が撮ったら、そうなるだろうなって。

立木:でも、正直に生きるのってけっこう難しいよ? 俺は思ったことをそのまま口に出しちゃうので、消したい発言もいっぱいある。でも、多くの人は周囲に対してある程度の忖度をしながら生きているよね。でないと、自分が傷だらけになってしまうから。
清水:とはいえ、立木さんってすごく柔軟じゃないですか。経験を積み重ねていくと、考え方とか思想が凝り固まっていくイメージがあるので、立木さんのスタンスにはすごく感銘を受けました。
たけもこ:失礼かもしれないんですが、立木さんが何歳であっても、私は友達になりたいなと思いました。
立木:これだけ年齢が離れているから申し訳ない気持ちもあるんだけどさ、俺も自分がすごく年上っていう感覚がないし、どこかに仲間意識があると思う。

たけもこ:すごく嬉しいです。SNSでいろんな人の言動を見ていると、自分らしさをもっと強く押し出さないといけないのかなと思うことも多いんですけれど、立木さんの写真を通じて自分にもっと正直になろうと思ったし、いろんな場所を旅して、瞬間ごとに思ったことをパッと文章にしたくなりました。
清水:僕はもっとシンプルに考えようと思いました。あと、含羞。恥ずかしいと思うことを大切にしようという考え方は、35歳を迎えて少し守りに入りそうになっている自分にものすごく刺さった感じがします。
あらためて、いろんな世界を体験するのは大事なことですよね。高城剛さんが「アイデアと移動距離は比例する」とおっしゃっていますが、本当にそうだと思うんです。自然との接し方も東京で暮らしているだけではわからないじゃないですか。遠く離れた北海道の大自然に足を踏み入れるから理解できることがある、みたいな。そこに再発見がある気がします。
立木:二人ともまだまだ若いじゃない。やりたい放題できるでしょ。あと、少しは横道に逸れたほうがいいよね。旅と同じで、ただただ真っ直ぐっていうのはつまらないよ。回り道をしながらいろんなことを経験し、それで一生を終えるほうが絶対に楽しいから。
All photos by Natsuko Kito