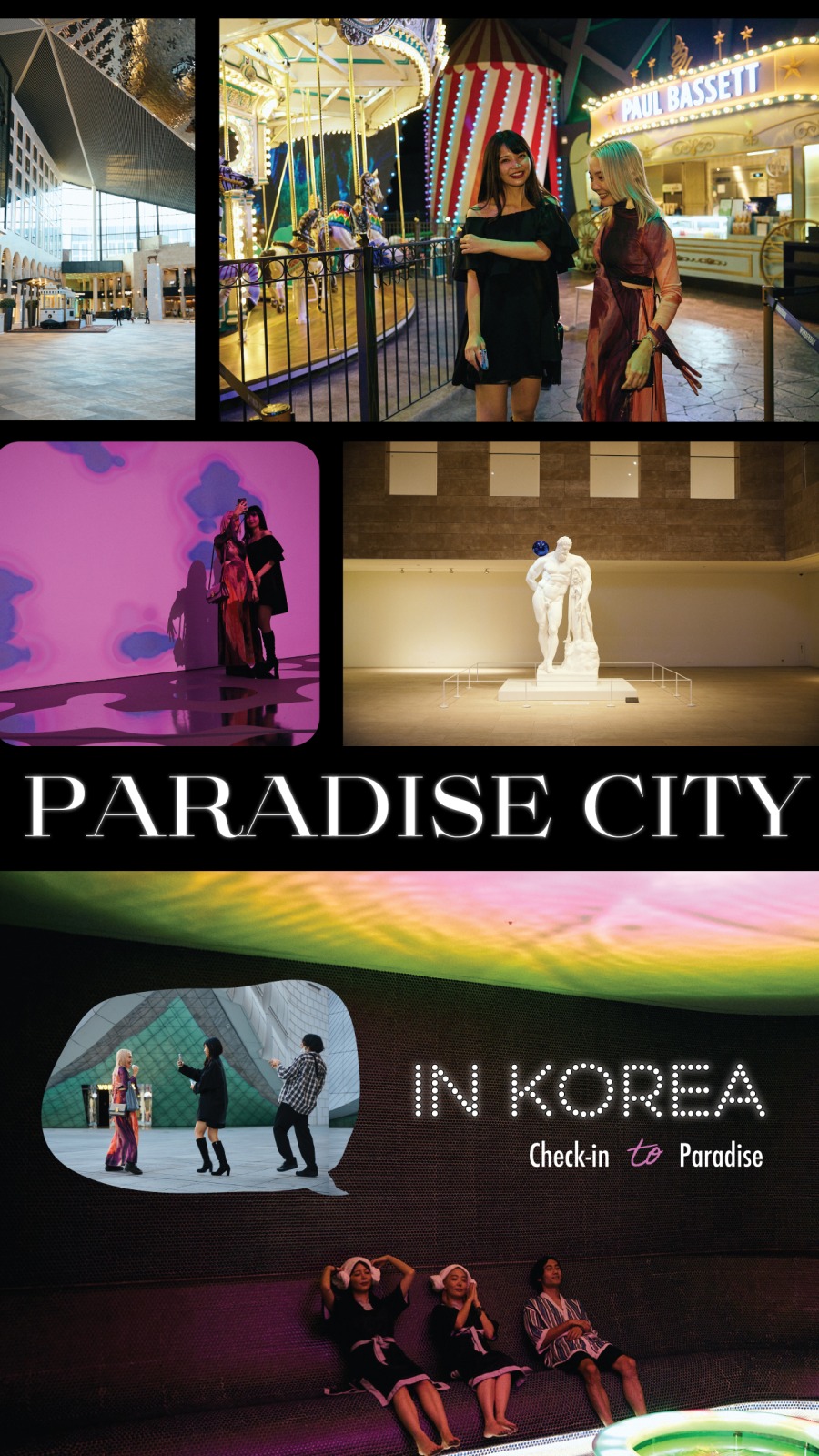この記事では、TABIPPOがつくりあげた最初の旅の本、『僕らの人生を変えた世界一周』のコンテンツをTABIPPO.netをご覧の皆様にもご紹介したいと考え、本誌に掲載している世界一周体験記を厳選して連載しています。
今回の主人公は、二木俊彦(当時31歳) です。
「世界一周」。それは、誰もが憧れる旅。でもその旅、夢で終わらせていいんですか?
人生最後の日のあなたが後悔するか、満足できるかどうかは今のあなたが踏み出す一歩で決まります。この特集では、そんな一歩を踏み出し、何も変わらない日常を生きることをやめて、世界中を旅することで人生が変わった15人の感動ストーリーを連載します。
\この記事は、書籍化もされています/

・二木俊彦(当時31歳) / 会社員 2010.3〜2011.4 / 375日間 / 35ヵ国
・世界一周の旅ルート
香港→マカオ→中国→ベトナム→ラオス→タイ→インド→ネパール→南アフリカ→ナミビア→ボツワナ→ザンビア→タンザニア→ケニア→マダガスカル→イギリス→フランス→ドイツ→チェコ→オーストリア→ハンガリー→ギリシャ→キプロス→ヨルダン→イスラエル→エジプト→スペイン→アメリカ→カナダ→メキシコ→ペルー→ボリビア→ブラジル→ウルグアイ→チリ
死んだ眼をしたサラリーマン

photo by Shutterstock
「死んだ眼をしたサラリーマン」日本の会社員を揶揄した言葉。私もその一人だった。
朝9時に出社し、気がつけば時計は22時過ぎ。こんなことを、週に5×50回。それが私の1年。結局、世界一周に出るまで、これを9回繰り返した。
働きだして4年目のことだろうか。ふとした縁をいただいて、「理想の大人たち」に出逢えた。会社の社長やオーナー、若い個人経営者の方々、「目標」と「目的」を持って生きている人たちは、本当に輝いて見えた。サラリーマンだけが人生ではないことを知り、少しずつ世間の見え方が変わっていったのを覚えている。
そして、ワーキングホリデーで1年、世界一周で1年、2年間かけて世界を旅したいなぁという夢ができた。(ワーキングホリデーで海外に行けるのは、30 歳まで。じゃあ29歳までは、この会社で頑張ってお金を貯めよう)
サラリーマンを続けた日々。全国各地に飛び散った同期の仲間と励まし合う。「数字はどうだ?」「インセンティブはとれそうか?」会社員としても中堅の立場となり、仕事の楽しさも知り、そこそこサラリーマンも悪くないなと思っていた。だから、この仕事を捨てるのは怖かったし、不安だった。
普通の人が世界一周なんて、できない
どこかで思っていた。(やっぱり普通の人が世界一周なんてできるわけない!)何の特徴も取り柄もない、おもしろみもない人間で、普通にこんな感じで、何となく仕事して、歳とって死んでいくのかなぁと思っていた自分がいた。
ガムシャラに働いていた20代、気づけば30歳を過ぎていた。夢だと思っていたワーキングホリデーの期限が終了。
過ぎてしまえば後の祭り。後悔の日々。(俺は夢だと勘違いしていただけだったのか?)すべての選択には賞味期限があると痛烈に思い知らされた。5年間貯めたお金で旅への諦めをつけるべく、車を買った。
その数ヵ月後、身近な人が突如、私の中で消えた。(人間には必ず終わりがあるんだよ)そう教えられた。それなら、死ぬ前に「これだけは叶えたんだから!人生後悔ないさ!」と言って、棺桶に入りたいと思った。
少し遅くなったけれど、やっと世界一周に行くことが腹落ちした。リーマンショック、再就職、現実の恐怖と闘いながら、私は31歳で会社を辞めた。
世界一周の旅は、リアルな RPG

photo by Shutterstock
失うものがなくなった375日間の世界一周の旅は、困難を乗り越え、レベルを上げ、出逢いと別れを繰り返す、私にとってはリアルなRPG(ロールプレイングゲーム)のようだった。荷物をパッキングし、旅へ出れば敵はたくさん!
まずはなんと言っても多種多彩な言語や文化、いかに日本が独自の世界なのか、痛いほど思い知らされる。その国の慣習、宗教、食事にトイレ、気候はもちろん、スリに置き引き、ストライキに強盗、敵はわんさか湧いてくる。
サラリーマンの常識は、世界の非常識
バスの廊下に平気で唾やタンを吐く中国人。先進国のフランスでは、道にゴミを捨てても OK。インドの電車のタイムテーブルは無意味だった。初歩的なカルチャーショックの数々。
日本の常識は、ましてや真面目で律儀なサラリーマンの常識は、世界の非常識でしかなかった。そして何といっても、私のこの旅最大の敵はタイで遭遇した睡眠強盗との戦いだった。
自称シンガポール人の男
ほんと、経験値稼ぎまくりというか、強制レベルアップ状態。舞台は、有名なカオサン通りから離れた一軒の屋台。
その日、僕はネパールから飛行機で到着し、トランジットだけすませ、次の日にはバリに向かうという軽い滞在のつもりだった。そんな僕に話しかけてくる、自称シンガポール人の男。
「最終便で来る彼女を待ってるんだ」本当かどうか聞くからに怪しい身の上話をしながら、時折「ビールをおごるよ」と言ってきたり、「ナッツ食べていいよ」と差し出してきたり。
(怪しいやつだなー)かなり僕は警戒していた。1 時間ほど経過した時だろうか?新しく自分で注文した瓶ビール。封はその場で開けてもらい、トイレに行く時も持っていっていたし、注意はしていた。しかし…。
「ナッツがカウンターにあるから取ってきてよ」
眩しい!と目が覚めた時には…

photo by Shutterstock
ほんの10秒もない時間だと思うのだが、ビール瓶から眼を離した隙に睡眠薬を入れられた。(…と思う)眩しいっ!と目が覚めた時には、私は見知らぬ場所の砂利の上でグッタリ寝ていた。
(あっやられたな)すぐに理解した。何時間寝ていたのだろう? 腕を見ると時計は取られていなかった。朝 6 時を確認する。意外と気分は落ち着いていて、「さて、警察だ」と立ち上がってまわりを見渡す。歩き出そうとすると、ポロッと何か足元に落ちた。
裸足のままで、知らない街の警察へ
それは、貴重品を腹巻きのように腰に巻き、服の中に隠しておくマネーベルトの切れ端だった。荒々しく引き裂かれ、ボロボロだった。現金もカードもパスポートも、何もない自分がそこにいた。そして、さらなる衝撃。足の裏が痛い?(あっ、サンダルまでない) 見たこともない街の中、裸足で警察を探した。
警察官は手馴れたもので、「大使館に行け」とのこと。(何で自分が…)なんてこと、思う暇すらその時はなく、とにかく、生きることだけに集中していた気がする。
私の冒険は完全に行き止まり。背に腹は変えられない。「おれ、裸足なんだ、何か靴くれ」と催促してみる。どこからともなく、緑のペラペラサンダルが出てきた。
そして気づいた。(大使館ってどこにある? そもそも場所が分かっても、俺には1円も金がない…)また、警察官に聞いてみる。
すると、透明なくじを引くようなアクリルの箱が出てきた。なんと、ドネーション用の箱(募金箱)。 そこから 120 バーツを取り出し、俺にくれた。「8 番のバスに乗れ」と。
バスに乗り込み、指定された停留所で降りてみる。(んんんっ?)どう見ても大使館らしきものは見当たらない。(くっ!あいつ間違って教えたな)
(さて、どうする?)頭を巡らす。…情報はもちろん一切なし。見渡すと、バス停の前に小さな商店があった。英語が通じるか分からないが聞くしかない。
差し出されたパンと一握りの紙切れ
おばちゃんに聞いてみる。
「すいません。大使館はどこですか?」
「・・・・・」
通じない。はてどうする?おばちゃんはおとうちゃんに交代する。